【2025年最新版】AIエージェントがビジネスを「超進化」させる。主要企業の取り組みから活用事例まで徹底解説(3)

はじめに
近年、AI技術の進化は目覚ましく、特にAIエージェントがビジネスの様々な場面で注目を集めています。
まるで人間のオペレーターのようにタスクをこなし、自律的に動くAIエージェントは、特にスタートアップ企業において新たな可能性を切り開いています。
この記事では、AIエージェントの最新動向や、主要なスタートアップ企業や業界ごとの具体的なユースケースを幅広くご紹介します。
海外におけるAIエージェントスタートアップの主な動向:
米国が牽引するイノベーション
海外における主な動向として、まずは世界のイノベーションを牽引する米国に目を向けてみましょう。
特にシリコンバレーは、AI技術の研究開発と投資において、揺るぎない中心地であり続けています。
AIエージェントの分野でも、この傾向は非常に顕著です。
なぜ米国ではこれほど開発が活発なのでしょうか?
その理由の一つは、世界トップクラスのベンチャーキャピタル(VC)やGoogle、Microsoftといった大手テック企業からの積極的な投資が行われていることです。
これらの資金が、革新的なアイデアを持つスタートアップの成長を力強く後押ししています。
また、優秀なエンジニアや研究者が集まるエコシステムも、新たなAIエージェントサービスが次々と生まれる土壌となっています。
米国では、汎用的なAIエージェント開発プラットフォームを提供する企業から、特定の業界に特化したソリューションまで、多岐にわたるスタートアップが登場しています。
彼らは、様々な業務の自動化や効率化、さらにはこれまで不可能だった領域でのAI活用を追求しており、世界中のビジネスに大きな影響を与えつつあります。
ここからは、海外、特にAIエージェントの最先端を走る米国のスタートアップ企業に焦点を当てて、その具体的な動向やサービスをご紹介します。
彼らがどのようなAIエージェントを開発し、ビジネスにどのような変革をもたらしているのかを見ていきましょう。
Artisan「Ava」
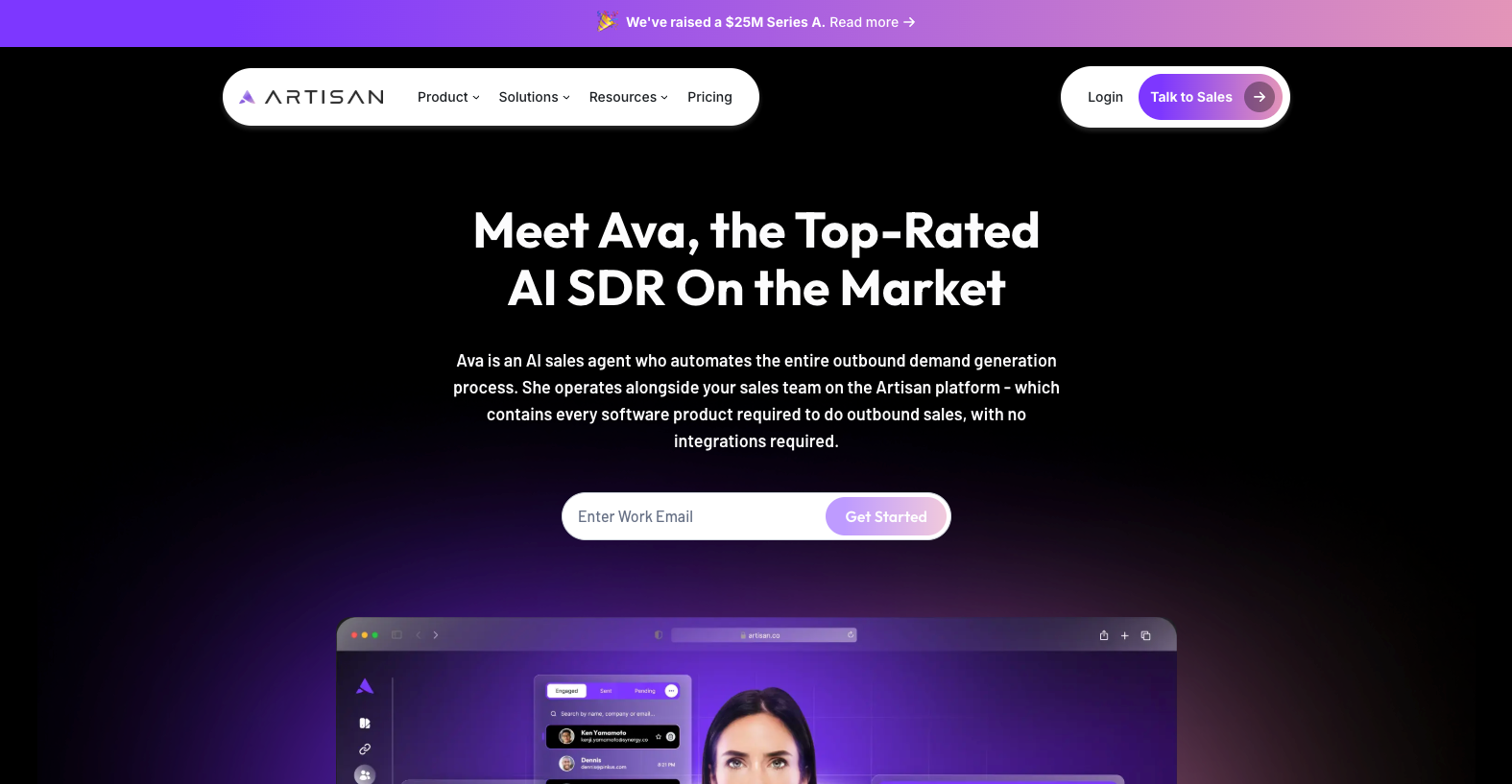
Artisanは、営業活動をAIの力で劇的に効率化するAI営業エージェント「Ava」を提供しているスタートアップです。
営業担当者(SDR: Sales Development Representative)の業務を自動化し、強力に支援してくれます。
AI営業エージェント「Ava」が変える営業の現場
「Ava」は、見込み顧客の特定からアプローチ、さらには顧客とのエンゲージメント(関係構築)までの一連のプロセスをAIが自動で行ってくれます。
例えば、どの顧客にいつ、どのようなメッセージを送るのが効果的かといった分析や実行をAIが担うため、営業担当者はより戦略的な提案や、人間にしかできない細やかな顧客対応に集中できるようになります。
営業チームにとって時間の節約はもちろん、成果向上にも直結しそうです。
Artisanは、2024年9月に1,200万ドル、2025年4月にはさらに2,500万ドルのシリーズA資金を調達しており、その成長性と市場からの期待の高さが伺えます。
Virtue AI
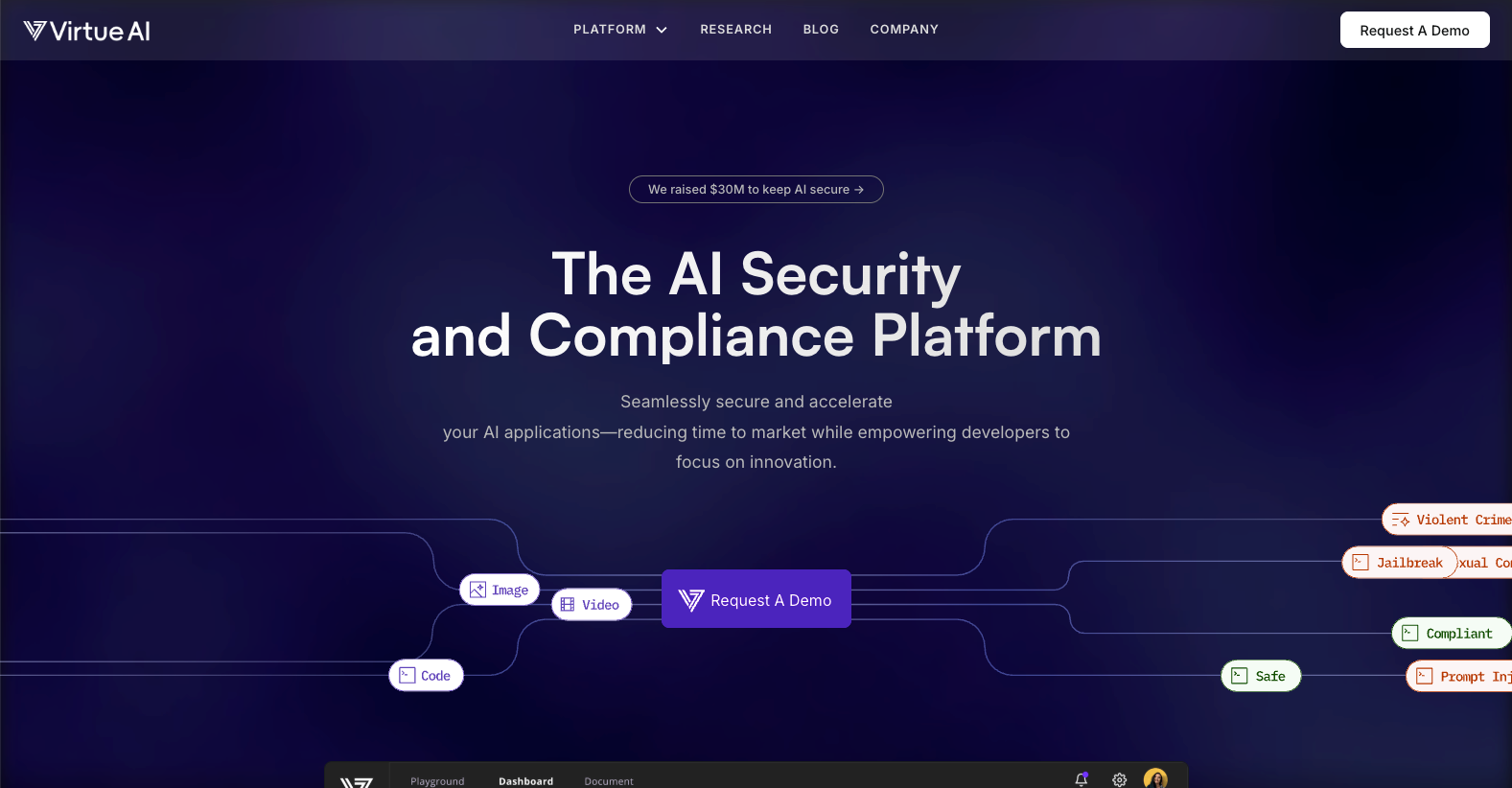
Virtue AIは、AIシステムのセキュリティ強化を目的とした、少し専門的ながらも非常に重要なプラットフォームを提供しています。
特に、ChatGPTのような大規模言語モデル(LLM)やそれを使ったアプリケーションの安全性、信頼性、そしてコンプライアンス(法令遵守)を確保することを目指しています。
AIの信頼性を高めるセキュリティプラットフォーム
AIが私たちの生活やビジネスに深く浸透するにつれて、その安全性をどう確保するかが大きな課題となります。
例えば、AIが不正確な情報を生成してしまったり、偏った判断をしてしまったりするリスクも考えられます。
Virtue AIのプラットフォームは、そうしたAIのリスクを未然に防ぎ、AIが常に安全で信頼できる形で機能するための「見張り役」のような存在となってくれるので、企業は安心してAIを導入し、活用できるようになります。
Walden Catalyst VenturesとLightspeed Venture Partnersという著名なベンチャーキャピタル主導で3,000万ドルを調達しており、AIの安全性に対する市場のニーズの高さが伺えます。
Breakout
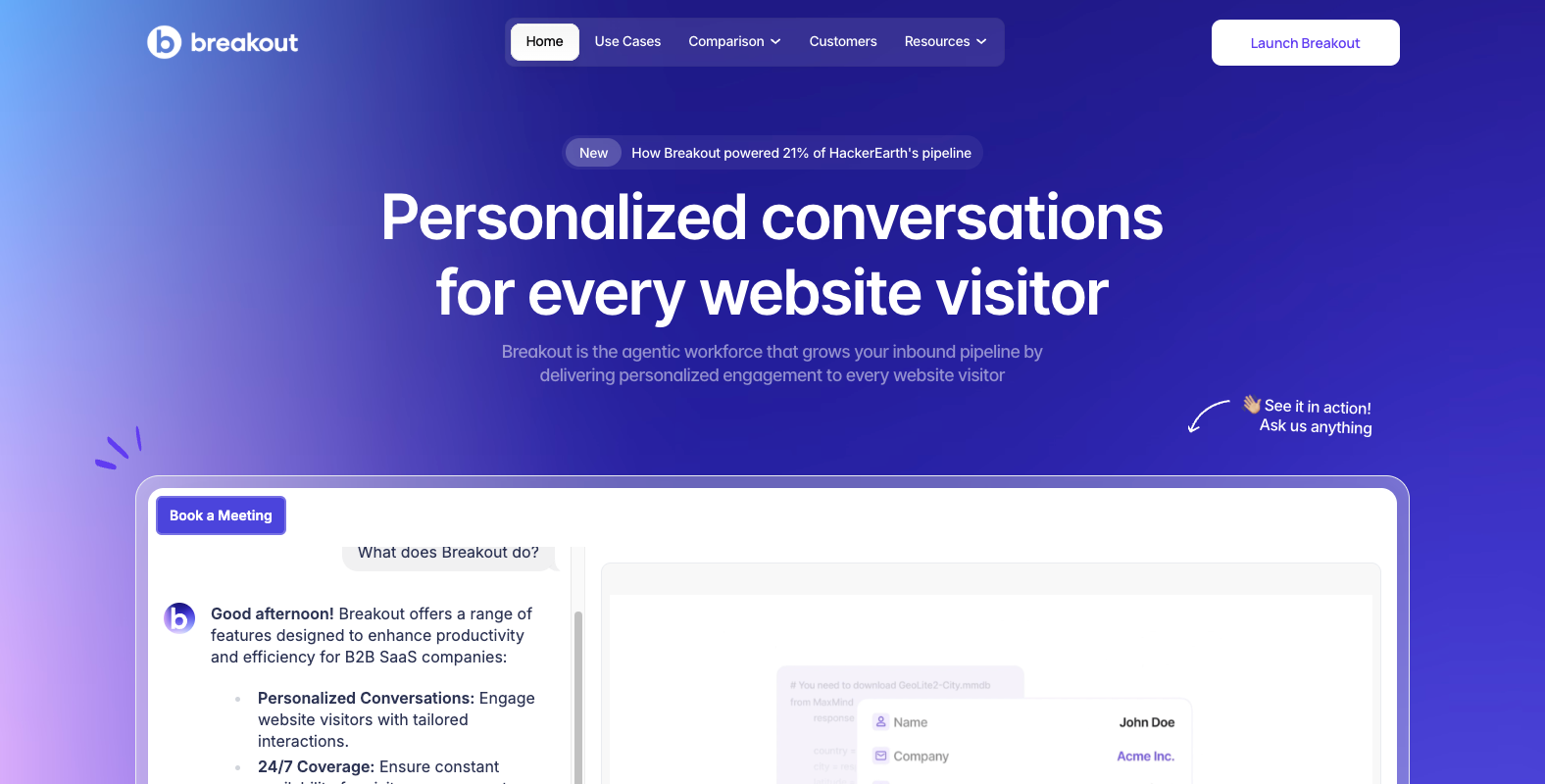
Breakoutは、元Googleの社員によって設立されたスタートアップで、こちらも営業分野に特化したAIエージェントを提供しています。
リード(見込み顧客)の特定から、具体的なアプローチ戦略の最適化、さらには顧客とのやり取りの分析までを自動で行ってくれるのが特徴です。
営業活動をスマートにするAIエージェント
Breakoutが提供するAIエージェントは、営業チームが「誰に、いつ、どのようにアプローチすれば最も効果的か」という問いに対する答えをAIが見つけてくれます。
例えば、膨大なデータの中から、自社の製品やサービスに最も関心を持つ可能性のあるリードを特定したり、そのリードに響くようなパーソナライズされたメッセージを提案したりします。
さらに、顧客とのエンゲージメント状況を分析することで、次のアクションを最適化してくれるのです。
営業担当者はより効率的に、そして賢く営業活動を進められるようになり、営業の生産性を飛躍的に高めるツールと言えそうです。
同社はVillage Global主導で325万ドルのシード資金を調達しており、その革新的なアプローチが評価されています。
Basis
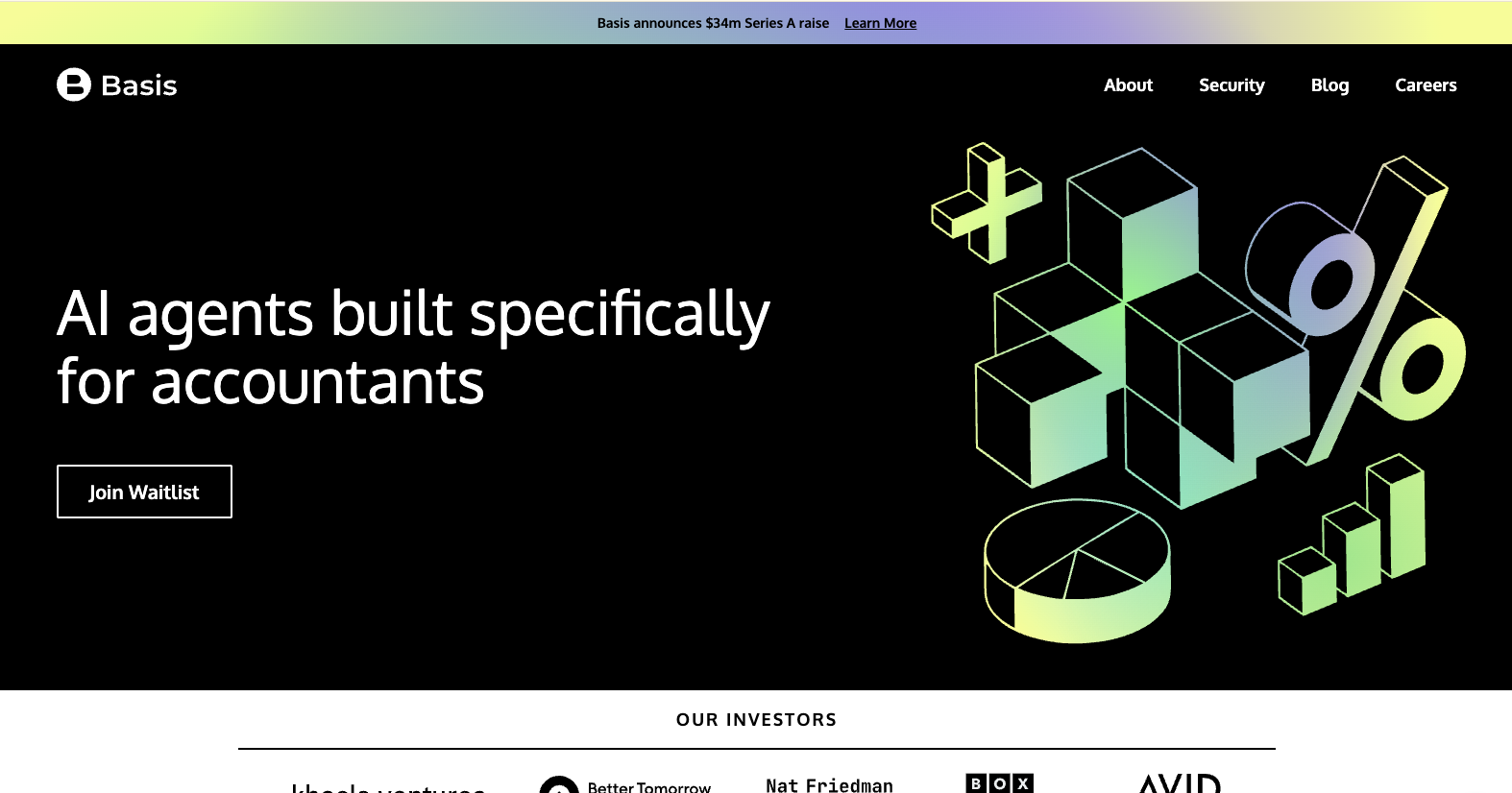
Basisは、企業にとって非常に重要な経理・会計業務の自動化に特化したAIエージェントを提供しているスタートアップです。
日々の業務で発生する請求書や領収書のデータ入力、仕訳(取引を帳簿に記録すること)、勘定照合(帳簿の残高が合っているか確認すること)といった作業をAIが代わりに行ってくれます。
経理業務をAIが丸ごとサポート
経理の仕事は、正確性が求められる上に、手作業が多く時間もかかります。
BasisのAIエージェントは、これらの定型的な作業を自動化することで、人的ミスを減らし、大幅な時間短縮を実現します。
AIが勝手に領収書を読み取って入力し、自動で仕訳をしてくれるとしたら、経理担当者はもっと重要な分析業務や経営戦略の立案に集中できるでしょう。
企業経営にとっても非常に大きなメリットをもたらすに違いありません。
Khosla Ventures主導で3,400万ドルのシリーズA資金を調達しており、その革新性が高く評価されていることがわかります。
Cognition「Devin」
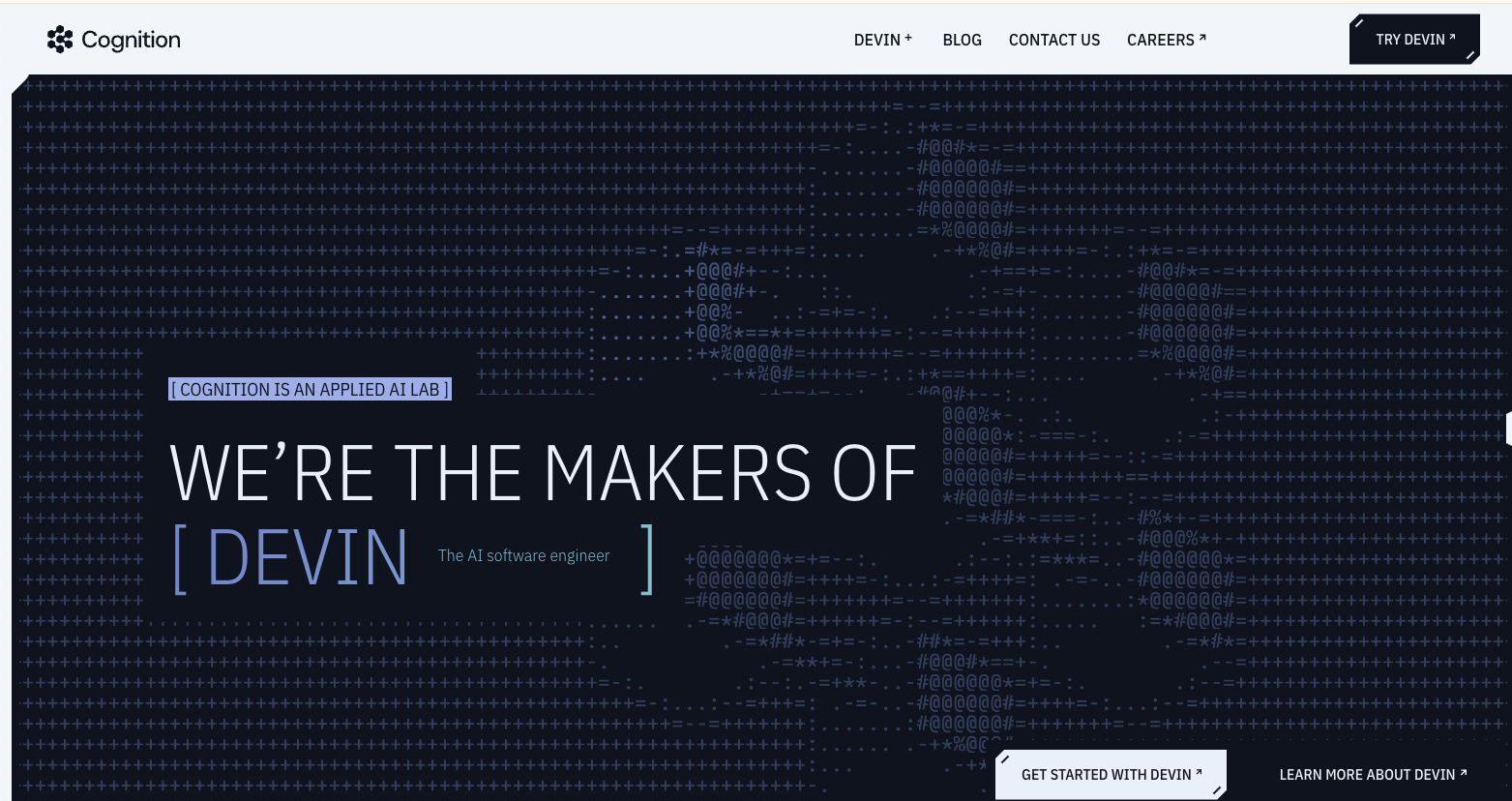
Cognitionは、AI分野で最も注目されているスタートアップの一つです。
彼らが開発したのは、自律型AIソフトウェアエンジニア「Devin」という驚くべき存在です。
「Devin」は、まるで人間のソフトウェアエンジニアのように、自然言語で与えられた開発の要望(例えば、「こういう機能を持ったアプリを作ってほしい」といった指示)に基づいて、自ら開発計画を立て、コードを書き、バグを見つけて修正し、必要なツールを使いこなしてソフトウェア開発プロジェクトを完了させる能力を持つとされています。
AIが自分でソフトウェアを開発する時代へ
「Devin」の登場は、ソフトウェア開発の世界に革命をもたらす可能性を秘めています。
これまで人間が何時間もかけて行っていたコーディングやデバッグ作業をAIが自律的にこなせるようになることで、開発スピードが格段に上がり、より複雑で高度なソフトウェアが効率的に生み出されることが期待されます。
Cognitionは2024年初頭にFounders Fundなどから1億7,500万ドルという巨額のシリーズA資金を調達しており、その評価額はなんと20億ドルに達したと報じられています。
市場での期待の高さが伺えますね。
11x「Alice」「Jordan」
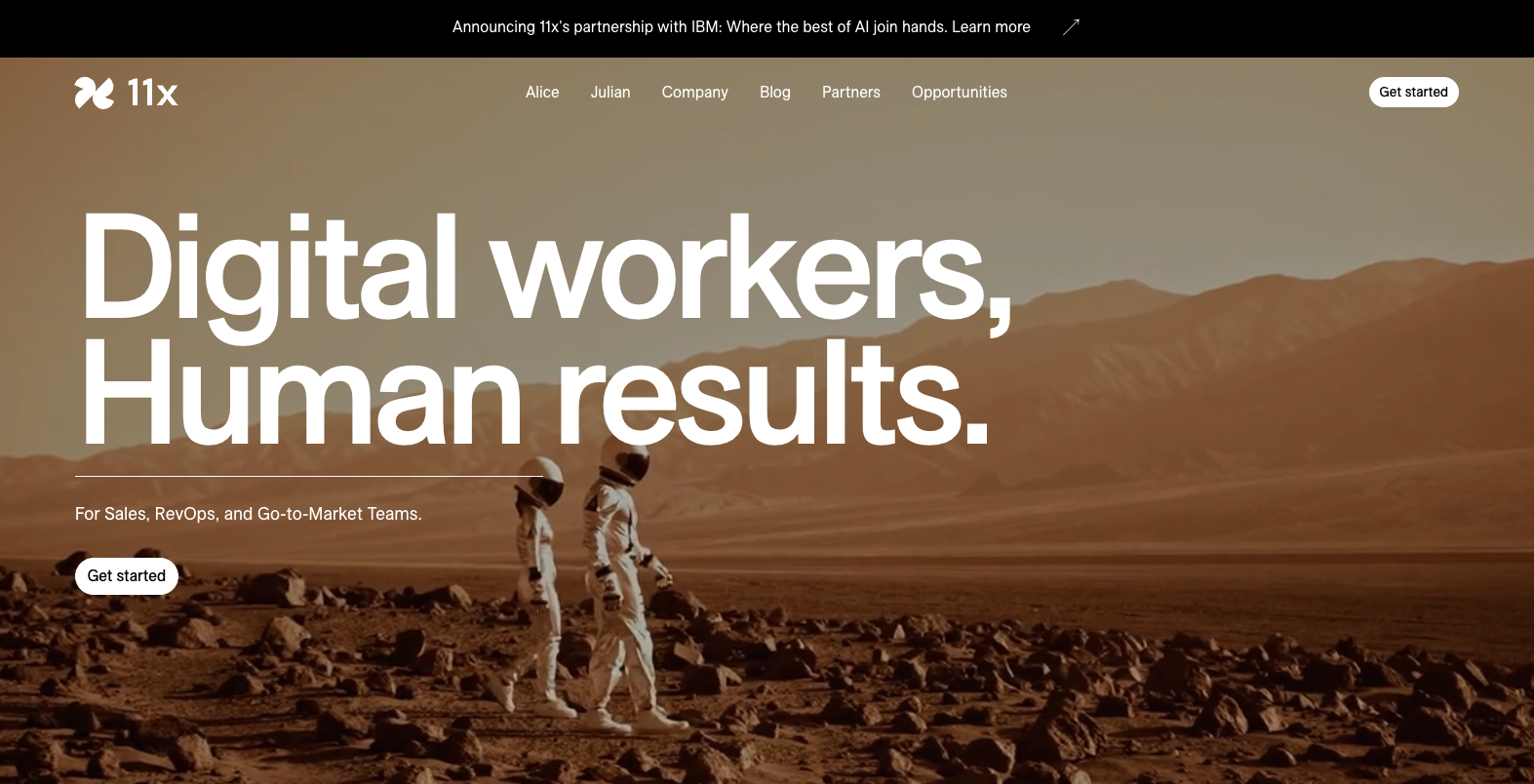
米サンフランシスコを拠点とするスタートアップの11xは、営業開発(SDR)業務を代替する「Alice」と、インバウンド・アウトバウンドの電話業務を担う「Julian」という、二つの自律型デジタルワーカーを展開しています。
デジタルワーカーが営業の最前線を支える
AIエージェント「Alice」は、潜在的な顧客を見つけ出し、彼らに響くメッセージを自動で作成して送ったり、商談の進行状況を管理したり、さらにはスケジュール調整まで行ってくれます。
一方、「Jordan」は、見込み顧客からの問い合わせにリアルタイムで対応したり、顧客のニーズをヒアリングしたり、電話でのスケジュール調整を行ったり、顧客管理システム(CRM)の情報を自動で更新したりと、電話対応の業務をまるごと引き受けてくれます。
これらのAIエージェントが人間に代わって働くことで、営業チームは顧客との関係構築や提案活動など、より創造的な業務に集中できるようになります。
営業の自動化は、本当に効率的で画期的な取り組みです。
11xは2024年にBenchmark主導で2,400万ドル(約35億円)のシリーズA資金調達を完了しており、そのポテンシャルが評価されていました。
しかし、華々しいデモンストレーションの裏で、実際のプロダクト運用において多くの課題が浮上し、事業が急速に失速したとも報じられています。
このような動きは、最先端のAI技術を実社会に導入する難しさを示しているのかもしれません。
Writer「AI Studio」
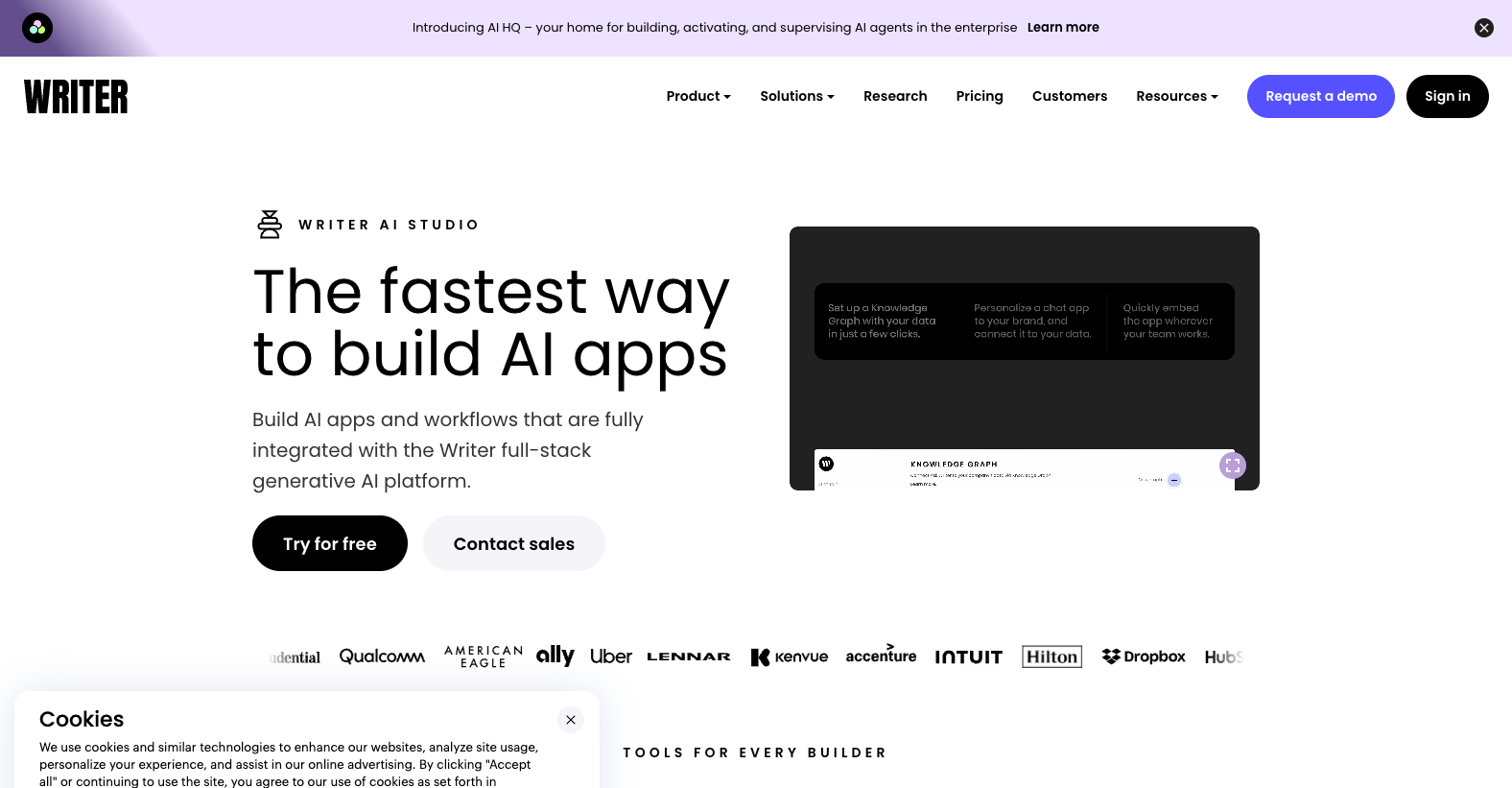
Writerは、「AI Studio」という多機能なAIツール群を提供しているスタートアップです。
企業が普段の業務で多くの時間とコストをかけている、例えば商品やサービスの説明文を書いたり、顧客サポートのよくある質問(FAQ)を作成したり、広告のキャッチコピーを考えたりといった「雑務」を、AIが素早くこなしてくれる役割を果たしています。
AI Studioが企業のコンテンツ作成を革新
このAI Studioは、まるで専属のコンテンツクリエイターがいるかのように、高品質な文章を瞬時に生成してくれます。
この機能によって、マーケティング担当者やカスタマーサポート担当者は、文章作成にかかる時間を大幅に削減し、より戦略的な業務や創造的な活動に集中できるようになります。
大手化粧品メーカーのロレアルや、配車サービスのウーバー、さらにはビジネスソフトウェア大手のセールスフォースといった名だたる企業が顧客として名を連ねていることからも、その実力の高さが伺えます。
Writerはこれまでに累計3億2,000万ドル(約460億円)もの資金を調達しており、評価額は19億ドル(約2,700億円)にも達する「ユニコーン企業」(評価額が10億ドルを超える未上場企業)となっています。
顧客の売上継続率(NRR)も160%と非常に高く、多くの顧客が契約を拡大しているという実績も、その信頼性を裏付けています。
Decagon
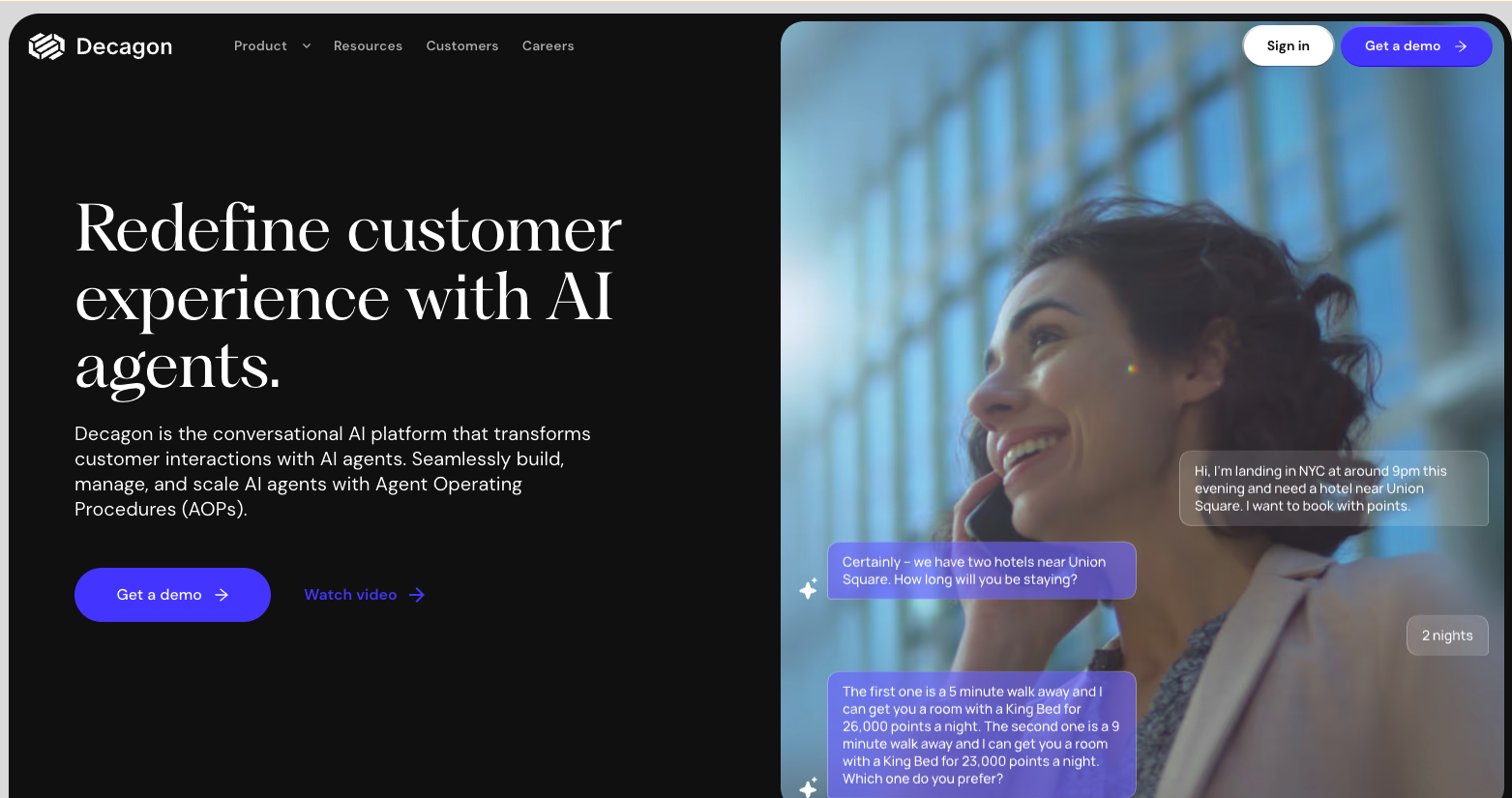
Decagonは、企業の顧客サポート向けAIエージェントに特化したサービスを提供しているスタートアップです。
アプリの操作方法に関する質問への応答、払い戻し処理、サブスクリプションのキャンセル処理など、顧客からの様々な問い合わせに対して、チャットボットやAIエージェントが自動で対応してくれるシステムを開発しています。
顧客サポートの未来をAIエージェントが創る
顧客サポートは、顧客満足度を大きく左右する重要な業務ですが、同時に非常に多くのリソースを必要とします。
DecagonのAIエージェントは、こうした定型的な問い合わせや手続きをAIが代行することで、顧客は待つことなくスムーズに問題を解決でき、企業側もサポートチームの負担を大幅に軽減できます。
導入企業の中には、サポートチームの規模を縮小したり、予測コストを大幅に削減できたという事例もあるほどです。
同社の年間経常収益(ARR)はすでに1,000万ドル(約14億円)を突破する見込みであり、評価額15億ドル(約2,150億円)で新たに1億ドル(約140億円)の資金調達に向けた交渉が進められていることからも、その事業の成長性が期待されていることがわかります。
彼らのAIエージェントは、OpenAI、Anthropic、Cohereといった最先端の大規模言語モデルを基盤としており、その高い性能と柔軟性も強みとなっています。
Martin
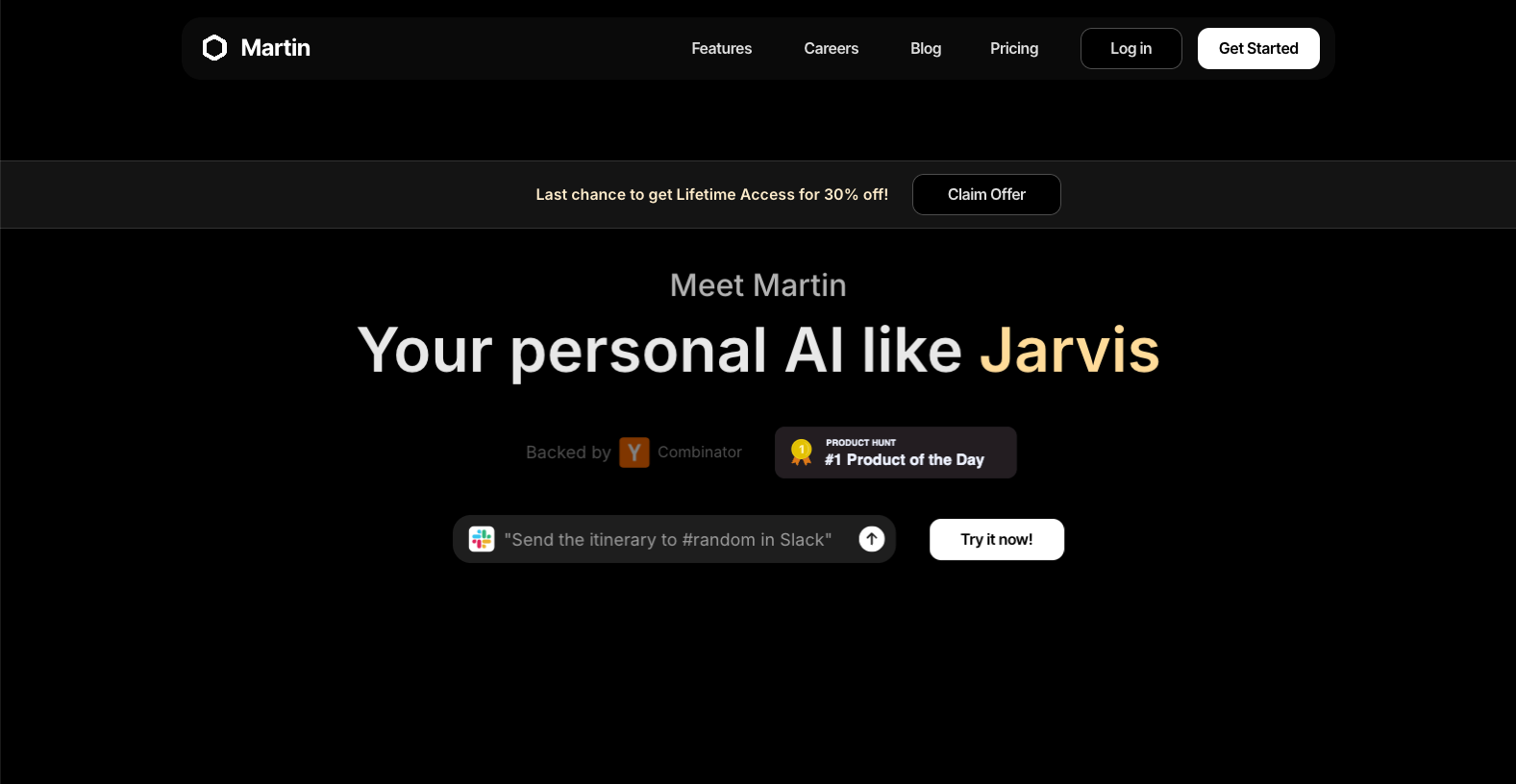
Martinは、イェール大学とUCバークレーを中退したという19歳のドーソン・チェン氏とイーサン・ホウ氏が率いる、非常に若いながらも注目を集めているスタートアップです。
彼らが開発しているのは、まるで秘書のように私たち個人の日常業務をサポートしてくれる「個人用AIアシスタント」です。
あなたの「脳」の代わりになるAIアシスタント
MartinのAIアシスタントのすごいところは、ただ指示されたことをこなすだけでなく、時間の経過とともにユーザーの好みや状況(コンテキスト)を深く理解していく「カスタムメモリアーキテクチャ」という独自の技術を持っている点です。
この技術によって、まるで長年連れ添ったパートナーのように、あなたのことをよく理解した上でサポートしてくれます。
電話、テキストメッセージ、メール、ビジネスチャットツールであるSlackなど、様々なコミュニケーションツールを横断的に活用し、カレンダーの管理、メールの返信、ToDoリストの管理、さらには電話やメッセージの送信まで、幅広いタスクを実行できるとのこと。
これは、日常業務を劇的に効率化してくれそうですね。
Martinは2025年1月には、有名なスタートアップ育成プログラムであるY Combinatorの支援を受け、200万ドルのシード資金調達を完了しており、その将来性が期待されています。
Hakimo

Hakimoは、監視カメラと連動して働く「AI警備員」を提供するスタートアップです。
人間の警備員が24時間体制で監視し続けるのは難しいですが、AIエージェントならそれが可能です。
24時間365日、安全を守るAI警備員
HakimoのAI警備員は、設置された全ての監視カメラからの映像を同時に監視し、侵入者やその他の怪しい動き、つまり「脅威」を自動で検知してくれます。
もし異常を検知した場合は、事前に設定されたルールに従って、音声での警告を発したり、警備会社へ自動で通知したり、場合によっては緊急サービス(警察や消防など)への要請まで行ってくれます。
これにより、人件費をかけずに24時間体制で高度なセキュリティを実現できるというわけです。
人間の警備員と同等のセキュリティサービスを、より低コストで提供することを目指しているとのこと。
これは、ビルや工場、倉庫など、様々な場所のセキュリティを強化する上で非常に心強い存在ですね。
Hakimoは新たに1,050万ドル(約15億7,000万円)を調達し、累計調達額は31億円に達しており、その技術とビジネスモデルが評価されています。
Mercor
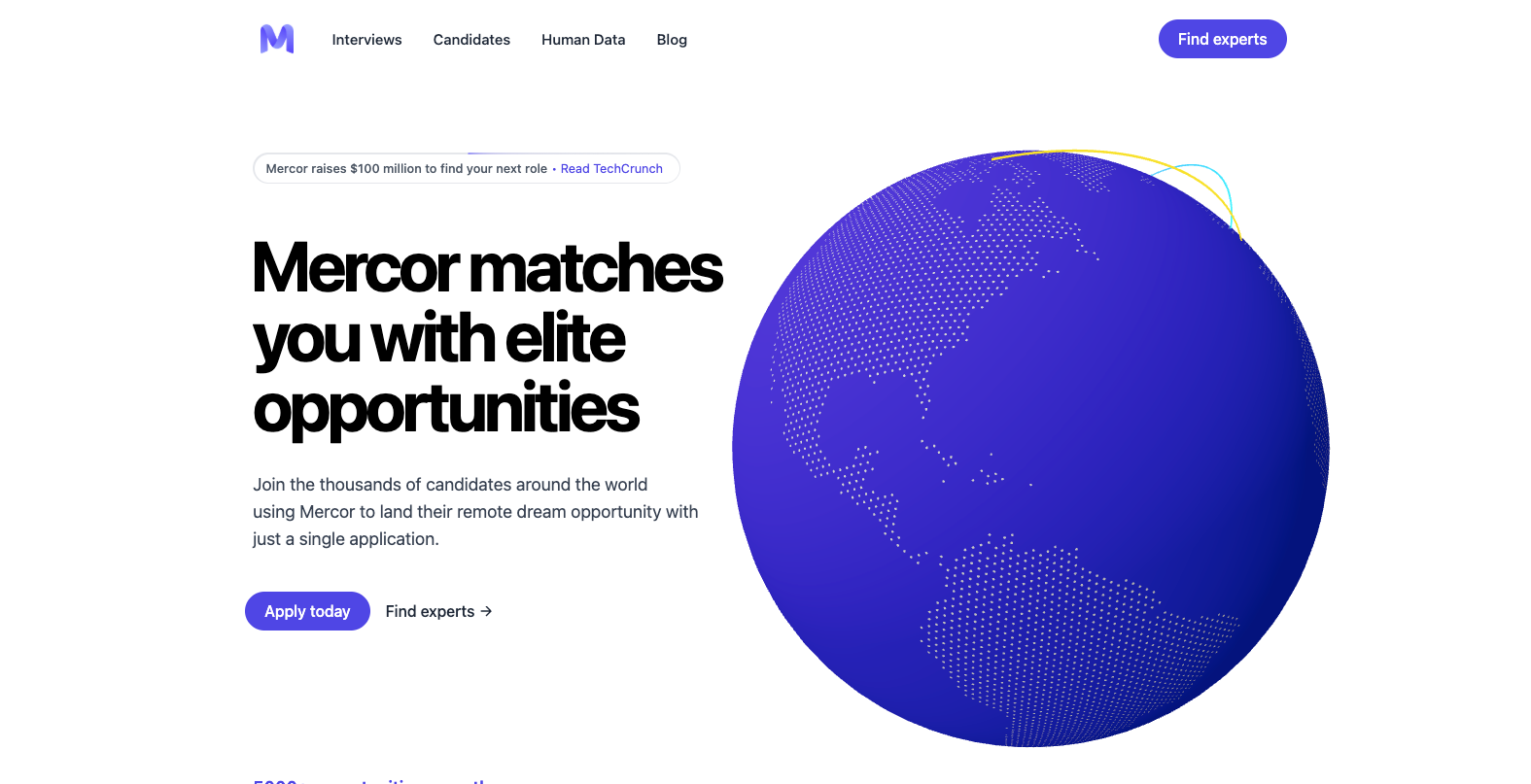
Mercorは、生成AIの技術をフル活用した採用プラットフォームを提供しているスタートアップです。
求職者がAIと約20分間面接をするだけで、その後のプロセスをAIが自動で進めてくれます。
AI面接官が採用プロセスを革新
Mercorのすごいところは、AI面接官が自然言語処理(NLP)と音声認識技術を駆使して、履歴書の確認から一次面接、さらにはその人にぴったりの求人マッチングまでを自動で行ってくれる点です。
企業は膨大な応募者の中から最適な人材を効率的に見つけ出すことができ、求職者側も自分のスキルや経験に合った仕事と出会いやすくなります。
設立当初、Mercorはインドのエンジニアと米国のスタートアップをマッチングさせる事業からスタートしましたが、わずか数ヶ月で年間収益が100万ドル(約1億4,300万円)規模にまで成長しました。
さらに、毎月50%という驚異的なペースで伸び続け、すでに黒字化も達成しているとのこと。
シリーズBラウンドで750万ドルを調達していることからも、その勢いがわかります。
Boardy
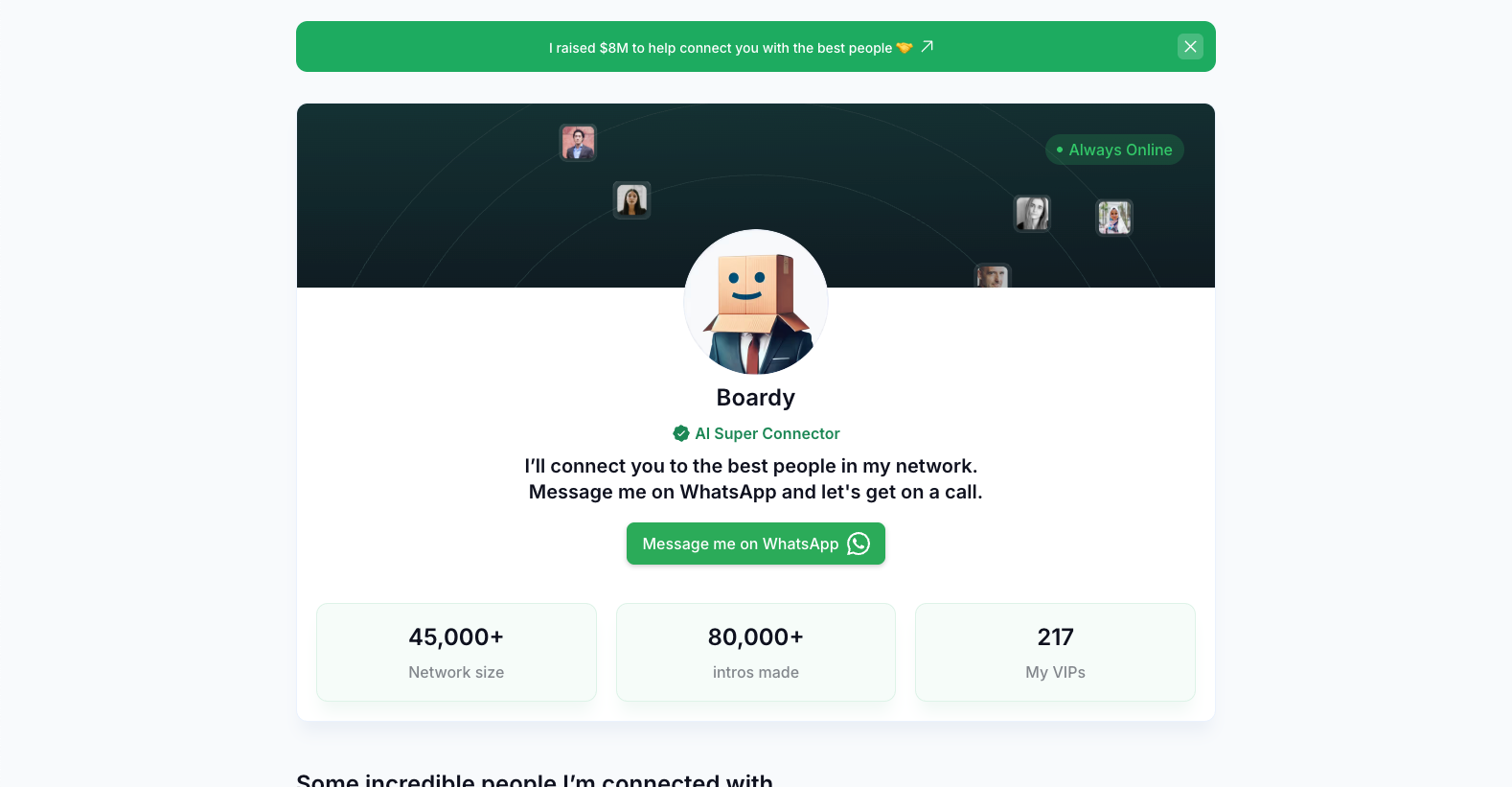
Boardyは、音声AIアシスタントを搭載した、これまでにないビジネスマッチングプラットフォームを提供しているスタートアップです。
音声AIアシスタントがビジネスの縁結び
Boardyの核となるのは、同名の音声AIアシスタント「Boardy」です。
このAIアシスタントが、ユーザーのキャリア、目標、興味、個性といった様々な情報に基づいて、最適なビジネスパートナーや協力者とのマッチングを自動的に行ってくれます。
さらに、音声から伝わるニュアンスや感情の情報までを分析に取り込むことで、より深く、人間的なつながりを感じさせるような高度なマッチングを実現していることが特筆すべきポイントです。
そして、Boardyのもう一つ驚くべき点は、今回のシードラウンドの資金調達において、創業チームが一切関与せず、有名なVC(ベンチャーキャピタル)であるCreandumとAIアシスタントであるBoardyの間で終始交渉が行われたという逸話です。
AI自身が資金調達を進めるなんて、まるでSFの世界が現実になったようです。
海外におけるAIエージェントスタートアップの主な動向:
中国が加速するAIイノベーションと競争
海外におけるAIエージェントの動向として、次に注目したいのが中国です。
中国でもAIエージェント技術への関心と、それに伴う投資が急速に高まっています。
では、なぜ中国でこれほどまでにAIエージェントの開発が活発に行われているのでしょうか。
その背景には、いくつかの要因が挙げられます。
まず、中国政府によるAI産業育成策という強力な後押しがあること。
AIエージェントの開発は、国家戦略として重点的に推進されており、政策面でのサポートが手厚いのです。
次に、アリババ、テンセント、バイトダンスといった国内の巨大テック企業が、自社のサービスにAIエージェントを組み込むために、積極的な投資と開発を行っていることが挙げられます。
彼らが持つ膨大なデータと資金力が、スタートアップの成長を力強く牽引しています。
さらに重要なのが、「百模大戦」と呼ばれる大規模言語モデル(LLM)の開発競争が激化していることです。
この熾烈な競争の中で、非常に高性能な基盤モデルが次々と生まれており、これらの強力なモデルがAIエージェント開発の「土台」となっています。
優れた基盤モデルがあるからこそ、より高度で複雑なタスクを実行できるAIエージェントを生み出すことが可能になっているということです。
まさに、国家レベルでのAI戦略と民間企業の力が融合し、技術競争がイノベーションを加速させる、という構図が中国のAIエージェント市場を力強く牽引していると言えるでしょう。
それでは、中国でどのようなAIエージェントが誕生し、どのような分野で活用されているのか、具体的なスタートアップ企業の事例を通して見ていきましょう。
Moonshot AI「Kimi」

Moonshot AI(月之暗面)は、長文のコンテキスト(文脈)処理に非常に強みを持つ大規模言語モデル「Kimi」を開発しているスタートアップです。
長い文章もスラスラ理解するAIモデル
AIモデルが長い文章や会話の内容を正確に理解し続けることは、実はとても難しい技術的な課題です。
「Kimi」は、この「長い文脈の処理」という点で突出した能力を持っています。
長い文脈の処理が可能となれば、膨大な量の資料を読み込んだり、複雑な議論の履歴を理解したりといった作業を、AIがより正確に、かつ効率的にこなせるようになるということです。
ビジネスにおける契約書の精査や研究論文の要約など、幅広い分野で活躍してくれる可能性を秘めていますね。
Moonshot AIは、2024年初頭にアリババなどから10億ドル(約1,500億円)を超えるという、まさに「巨額」と呼ぶにふさわしい資金を調達しました。
この技術力が市場からいかに高く評価されているかの証と言えるでしょう。
Baichuan AI

Baichuan AI(百川智能)は、中国の検索エンジン大手Sogou(捜狗)の元CEOが設立したスタートアップで、オープンソースとクローズドソースの両方で大規模言語モデル(LLM)を提供しています。
幅広いニーズに応える多角的なAIモデル戦略
オープンソースのLLMは、誰でも自由に利用・改変できるため、多くの開発者がその上に新たなアプリケーションを構築しやすいというメリットがあります。
一方、クローズドソースのLLMは、企業が独自の技術やデータを活用して、より高性能でセキュアなサービスを提供できる強みがあります。
Baichuan AIは、この両方のアプローチを取ることで、様々な企業のニーズに応えようとしているというわけです。
幅広い選択肢があるのは、ユーザーにとってありがたいですね。
同社は2023年後半に、アリババ、テンセント、シャオミといった中国を代表するテック企業から、約3億ドル(約450億円)もの資金を調達しました。
このことからも、中国のIT業界全体から大きな期待が寄せられていることがわかります。
Zhipu AI

Zhipu AI(智譜AI)は、中国のトップ大学の一つである清華大学から生まれたAIスタートアップです。
彼らは「GLMシリーズ」と呼ばれる大規模言語モデルを開発しています。
大学の知が詰まった先進的なAIモデル
大学発のスタートアップということもあり、Zhipu AIは最先端の研究成果をLLMの開発に活かしているのが特徴です。
「GLMシリーズ」のLLMは、その高度な技術力と学術的な背景に支えられており、様々なタスクにおいて高い性能を発揮するとされています。
これにより、企業はよりスマートなAIエージェントを構築し、ビジネスプロセスを最適化できるようになるでしょう。
アカデミックな強みが実を結ぶという、素晴らしい事例です!
Zhipu AIは2023年から2024年にかけて、アリババ、テンセント、Meituan(美団)、シャオミなど、再び多くの大手企業から複数回にわたり、総額25億元(約500億円)以上もの資金を調達しています。
これは、同社の技術力と将来性が高く評価されている証拠であり、中国のAI業界における重要企業としての地位を確立していることが伺えます。
MiniMax
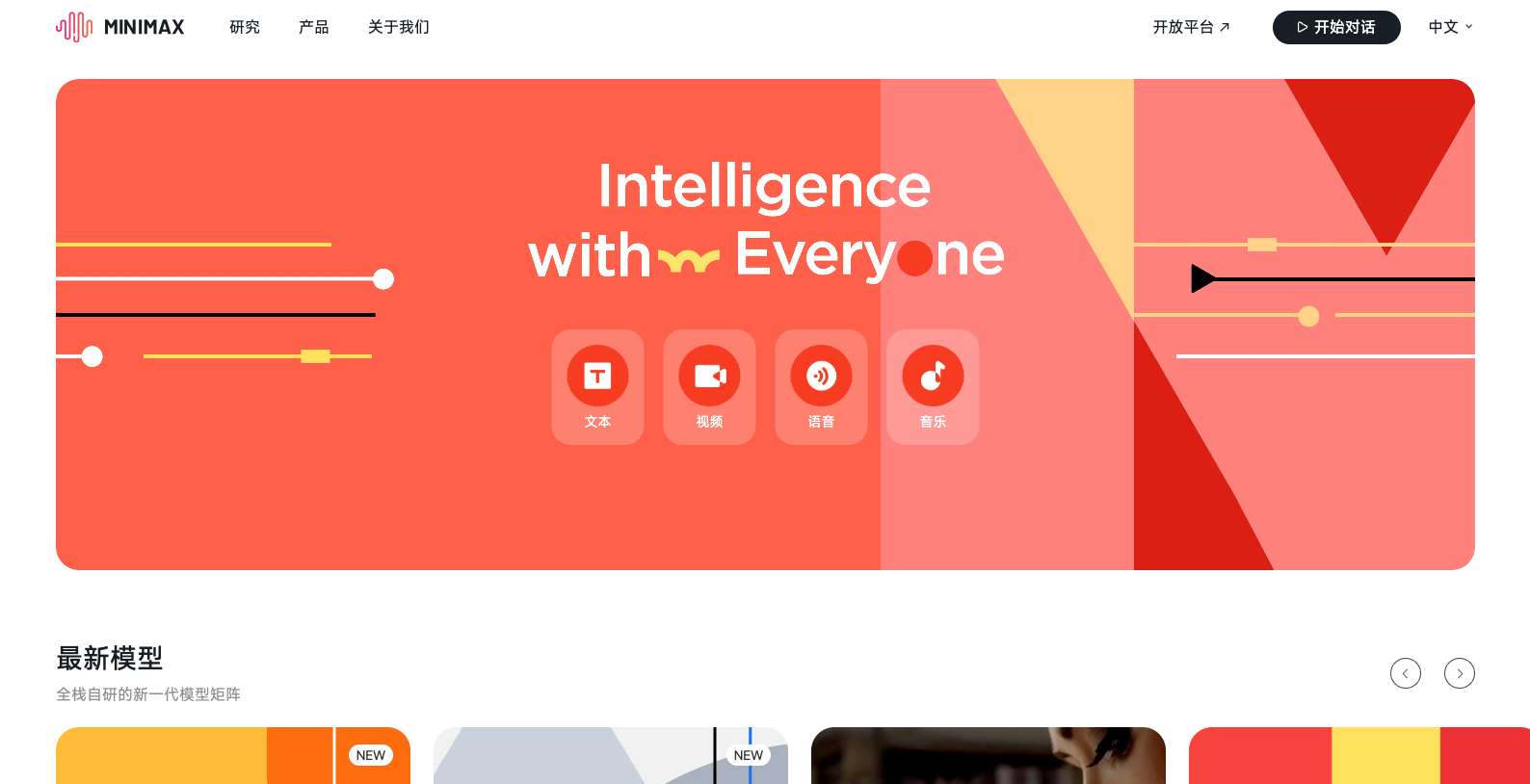
MiniMax(名之梦)は、テキストだけでなく、音声やビジュアルといった様々な形式の情報を処理できる「マルチモーダル」な基盤モデルを開発しているスタートアップです。
ゲーム分野での応用も積極的に進めています。
テキストも音声も画像も理解するマルチモーダルAI
マルチモーダルなAIとは、人間が五感で世界を認識するように、AIも複数の情報源(例えば、文字、音、画像)から情報を得て理解する能力を持つことを意味します。
MiniMaxのAIは、この能力によって、より複雑な状況判断や人間との自然なインタラクション(相互作用)が可能になっています。
ゲームの世界でAIキャラクターがよりリアルに反応したり、様々な情報を統合して最適な答えを導き出したりと、その応用範囲は無限大です。
MiniMaxは2024年3月頃、アリババが主導するラウンドで少なくとも6億ドル(約900億円)もの巨額の資金を調達しました。
この調達額からも、マルチモーダルAIへの期待の大きさが感じられます。
Lingyi Wanwu「Yi」

Lingyi Wanwu(零一万物)は、かつてMicrosoftリサーチアジアの所長を務め、Google Chinaのトップでもあった李開復(Kai-Fu Lee)氏という、AI業界の「レジェンド」とも言える人物が設立したスタートアップです。
彼らはオープンソースの大規模言語モデル「Yi」シリーズを開発しています。
AI業界のレジェンドが手掛けるオープンソースLLM
李開復氏のような著名な人物が手掛けるAIモデルということで、その技術力には大きな注目が集まっています。
「Yi」シリーズはオープンソースで提供されているため、世界中の開発者が自由に利用し、改良を加えることができます。
そのため、コミュニティ全体の知恵と力が結集され、より迅速な技術革新が期待されます。
Lingyi Wanwuは2023年後半にアリババクラウドなどから出資を受けており、その安定した開発体制が伺えます。
Monica「Manus」

Manusは、中国のスタートアップ企業Monicaによって2025年3月に公開された、非常に先進的な自律型汎用AIエージェントです。
指示一つでタスクを完遂する「自律型AIエージェント」
Manusの最大の特徴は、一度の指示を与えるだけで、AIが自らその内容を判断し、タスクの計画を立て、実行し、さらにはその結果を検証する、という一連のプロセスを全て自動で行える点にあります。
この高い自律性と、複雑なタスクを実行する能力は、世界中で大きな注目を集めました。
アイデアを形にするために、AIが自力で調べて、計画を立てて、実行してくれるなんて、すごい技術の進歩です!
実際に、Manusは34カ国・地域の検索キーワードランキングで上位にランクインするなど、その革新性が広く認識されています。
非同期バックグラウンド処理といった、作業を裏で効率的に進めることができる機能も備えており、その技術力の高さが伺えます。
DeepSeek

DeepSeekは、2023年5月に中国で設立された比較的新しいスタートアップです。
2025年1月には、非常に高性能な大規模言語モデル「DeepSeek-R1」を発表し、大きな話題となりました。
高性能かつ低コストなAIモデルで世界を魅了
DeepSeekが特に注目されているのは、その「高性能」であるにもかかわらず、「安価なコスト」でAIモデルを提供している点にあります。
これは、より多くの企業や開発者がAIを活用できる可能性を広げる、非常に重要な要素です。
さらに、驚くほどの速さで開発を進めていることも、その勢いを象徴しています。
短期間でこれだけの成果を出せるのは、本当にすごいことですね。
このコストパフォーマンスと開発スピードが大きな話題となり、DeepSeekは24カ国・地域の検索キーワードランキングにランクインするなど、世界的な注目を集めています。
海外におけるAIエージェントスタートアップの主な動向:
欧州が牽引する倫理的AIと専門分野のイノベーション
海外におけるAIエージェントの動向として、次に焦点を当てるのは欧州です。
米国や中国のような規模の巨額な資金調達のニュースは少ないかもしれませんが、欧州には独自の強みを持つ活発なAIエコシステムがしっかりと存在しています。
特に、フランス、ドイツ、英国がAI研究開発とスタートアップ創出の中心地となっており、独自の進化を遂げています。
では、なぜ欧州がAIエージェント開発において独自の道を歩んでいるのでしょうか。
その特徴と背景をいくつか解説します。
まず、EU AI Act(AI規則)に代表されるように、AIの安全性や倫理、プライバシー保護に対する意識が非常に高いことです。
これは、AI技術が社会に与える影響を深く考慮し、信頼できるAIシステムを構築しようとする欧州ならではの姿勢が反映されています。
そのため、AIエージェントの開発においても、こうした規制環境への適合や倫理的な側面に重点が置かれる傾向があります。
また、欧州のスタートアップは、B2Bソリューション(企業向けのサービス)や産業AI、そしてプライバシー保護技術といった特定の分野に強みを持っていることも特徴です。
これは、特定の業界が抱える課題解決や、データ主権の尊重を重視する文化が根付いているためと考えられます。
汎用的なAIの開発だけでなく、より実用的で、かつ信頼性の高いAIエージェントを社会に実装しようとする動きが活発に進められています。
欧州でどのようなAIエージェントが生まれ、どのような分野で活躍しているのか、具体的なスタートアップ企業の事例を通して見ていきましょう。
Mistral AI
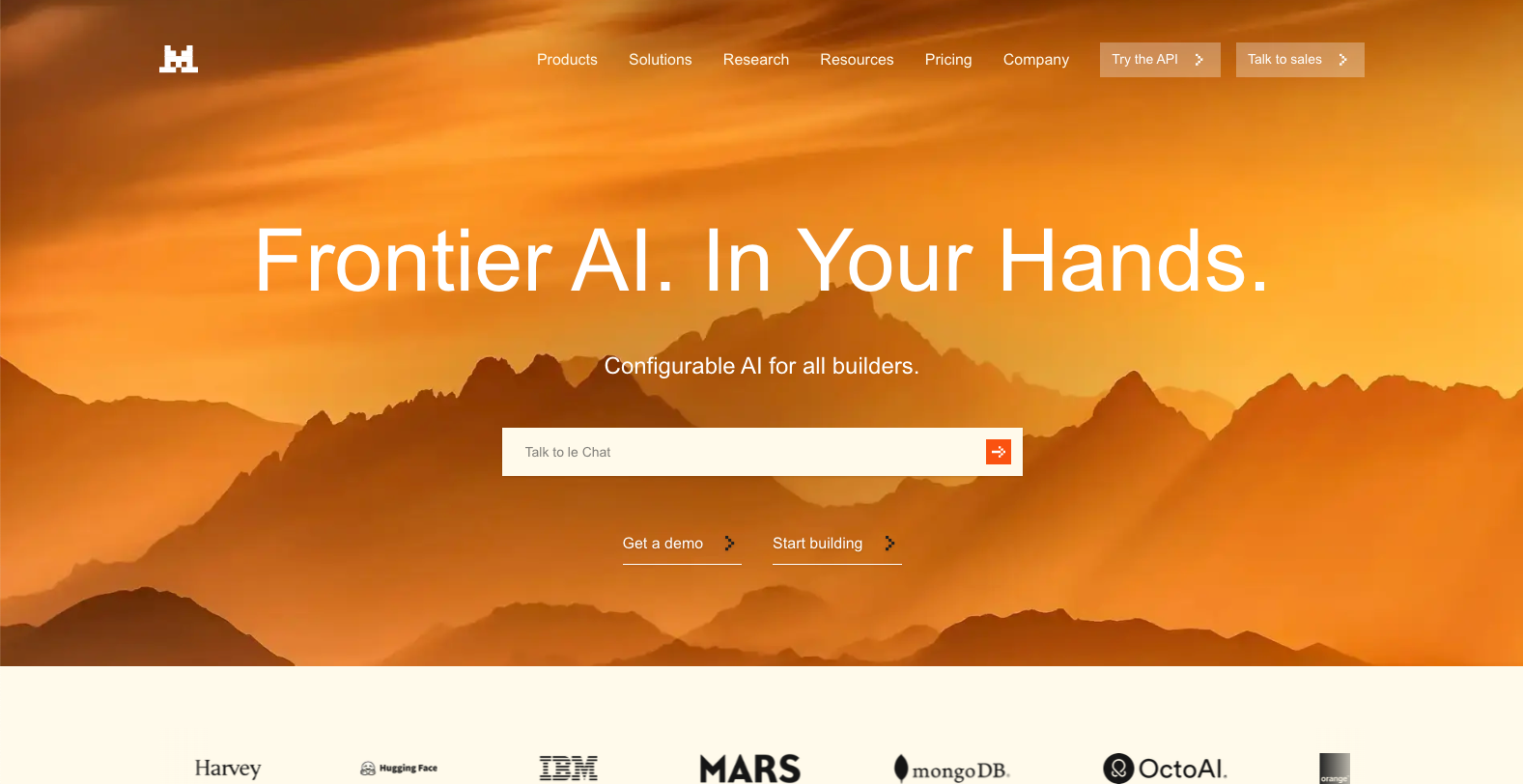
フランスに拠点を置くMistral AIは、オープンソース戦略を特徴とする大規模言語モデル(LLM)の開発企業です。
オープンソースでAIの可能性を広げる
Mistral AIの強みは、開発したLLMをオープンソースとして公開している点にあります。
これは、誰でも自由に彼らのモデルを利用し、改良したり、新しいアプリケーションに組み込んだりできることを意味します。
このアプローチにより、世界中の開発者や企業がAI技術を活用しやすくなり、AIエコシステム全体の発展を加速させることにつながります。
コミュニティの力でAIを育てていくのは、とても魅力的な取り組みですね。
2023年末から2024年初頭にかけて、Andreessen Horowitz (a16z) やLightspeed Venture Partnersといった著名なベンチャーキャピタルが主導し、さらにMicrosoftやNVIDIAといった大手企業も参加したラウンドで、約6億ユーロ(約960億円)という巨額の資金調達を実施しました。
これは、オープンソースLLMの可能性と、Mistral AIの技術力が世界的に高く評価されている証拠と言えるでしょう。
Aleph Alpha

ドイツを拠点とするAleph Alphaは、AIの「説明可能性」や「信頼性」、そして「データの主権」を特に重視した大規模言語モデル(LLM)を開発しているスタートアップです。
特に企業や政府機関での利用を意識したモデル作りを進めています。
信頼性と透明性を追求する「責任あるAI」
AIが社会に深く浸透するにつれて、「なぜAIがそのような判断をしたのか」という説明や、AIが常に信頼できる形で機能する保証が非常に重要になります。
Aleph Alphaは、この「説明可能性」や「信頼性」をAIモデルの核心に据えています。
また、データの管理や所在に関する「データの主権」を重視することで、特に機密性の高い情報を扱う企業や政府機関が安心してAIを利用できる環境を提供しています。
これは、AIの未来を考える上で、非常に重要な視点ですね。
2023年11月には、自動車部品大手のBosch(ボッシュ)やソフトウェア大手のSAP、さらにはドイツ最大の小売グループであるSchwarz Group(シュヴァルツ・グループ)などから、5億ドル(約750億円)のシリーズBラウンド資金調達を発表しました。
これは、彼らの掲げる「責任あるAI」へのアプローチが、産業界から大きな支持を得ていることを示しています。
Helsing
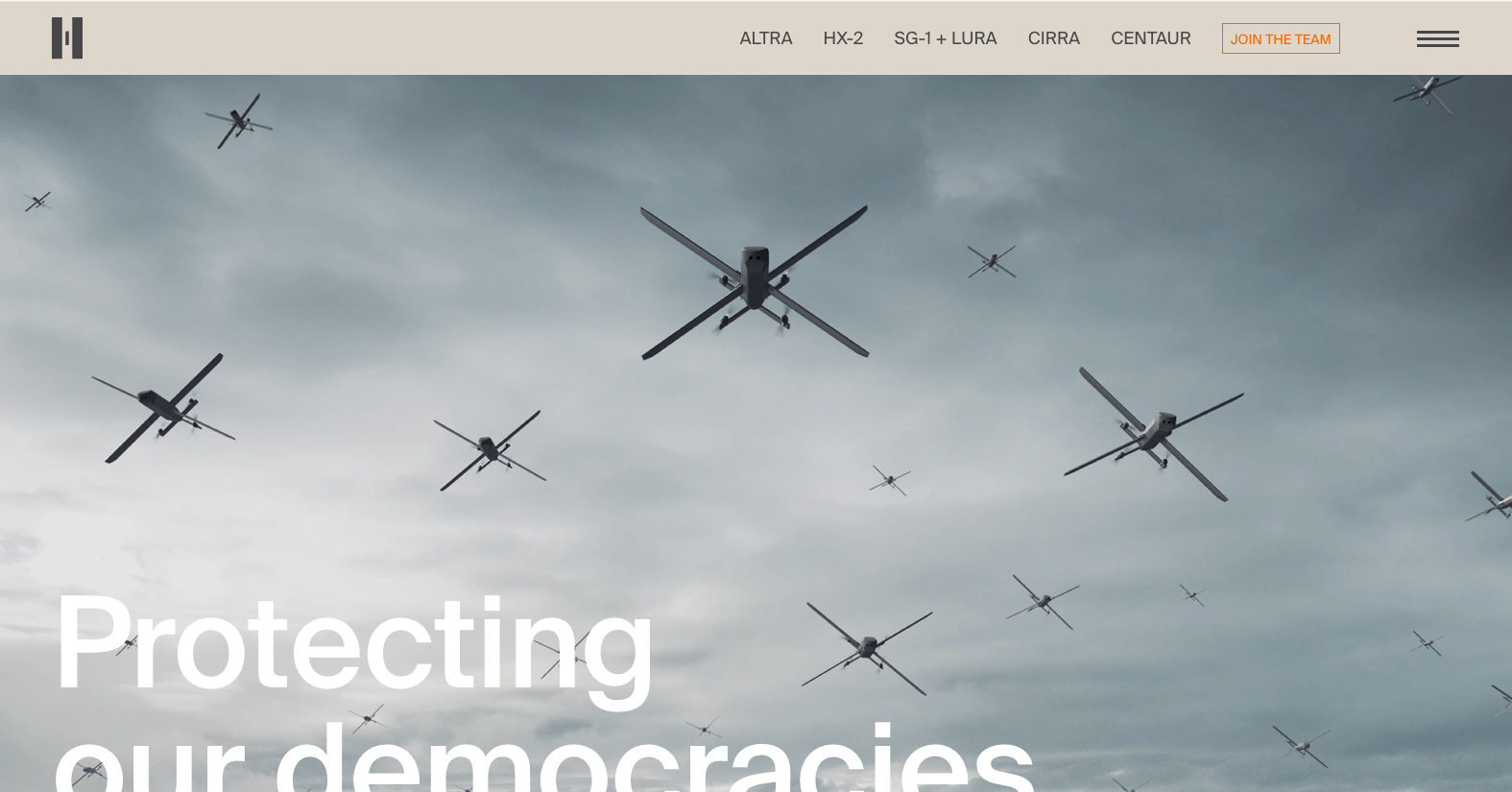
ドイツに拠点を置くHelsingは、防衛・安全保障分野に特化した軍事AI企業という、非常にユニークな立ち位置のスタートアップです。
防衛にAIエージェントの力を
Helsingは、リアルタイムでのデータ解析、刻々と変化する状況の認識、そして迅速な意思決定支援など、高度なAI技術(AIエージェント技術を含む)を駆使して、国の防衛能力の向上を目指しています。
例えば、広範囲の情報をAIが瞬時に分析し、複雑な状況を人間が理解しやすい形に整理したり、最適な行動計画を提案したりするような役割を担います。
これは、高度な専門知識と迅速な判断が求められる防衛分野において、AIが非常に大きな貢献をする可能性を示しています。
同社はシリーズBラウンドで2億900万ユーロ(約330億円)を調達しました。
この巨額の資金調達は、防衛分野におけるAI技術の重要性と、Helsingの技術力が評価されている証と言えるでしょう。
Maki People(マキ・ピープル)
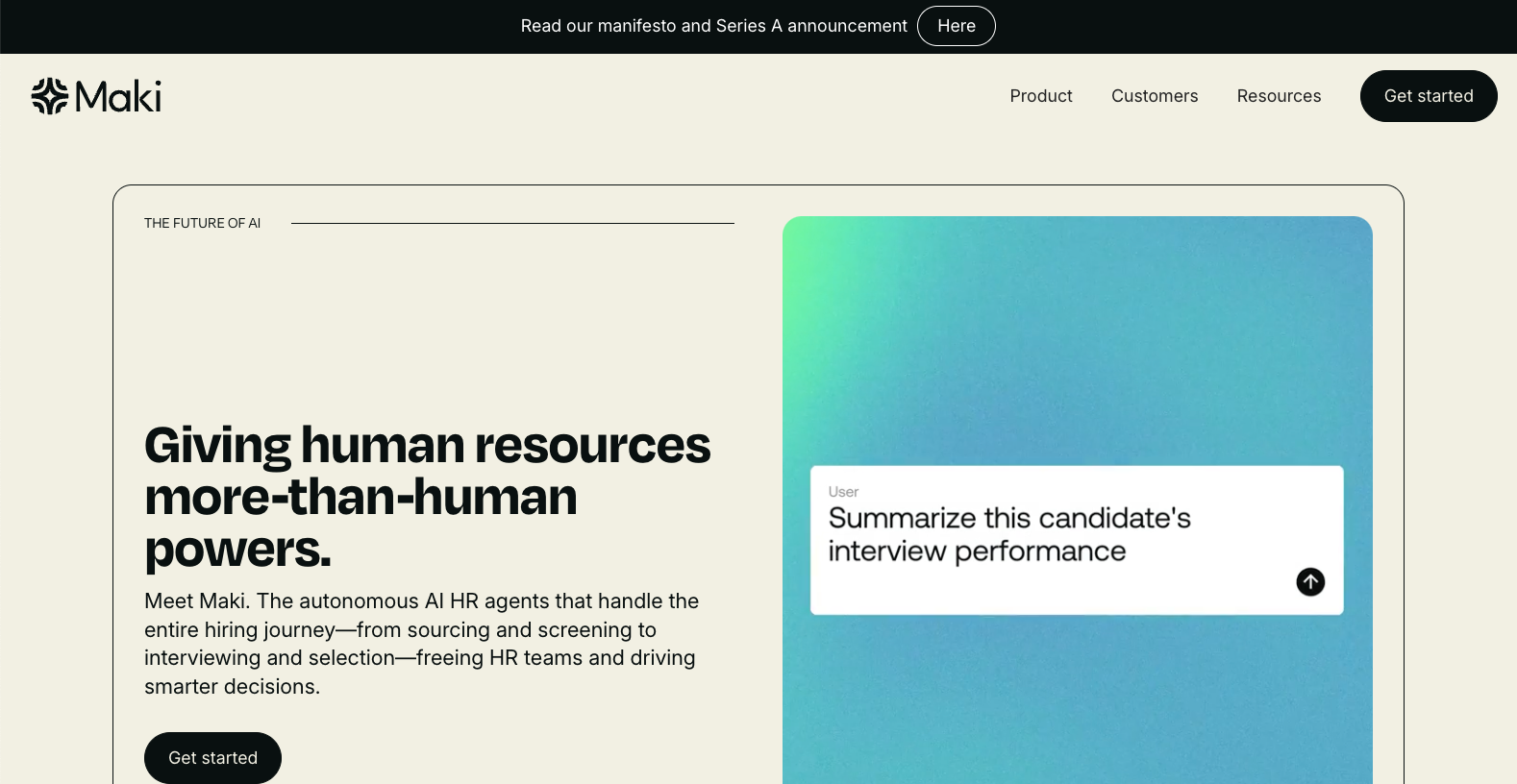
フランスのMaki Peopleは、人材獲得に特化した「会話型HRエージェント」を提供しているスタートアップです。
AIを活用したスキルテストや、偏りのないデータ分析ツールを使って、採用プロセスを効率化してくれます。
AIが採用のプロになってくれる
Maki PeopleのAIエージェントは、まるで優秀な人事担当者のように、採用活動の様々な場面で活躍します。
例えば、候補者のスキルをAIがテストしたり、履歴書や面接での情報を分析する際に、人間の無意識の偏り(バイアス)を排除して公平な評価をサポートしたりします。
このサポートによって、人事担当者の業務の80%が自動化されるというから驚きです!
音声、ビデオ、テキストといった複数の形式に対応できる「マルチモーダル」な点も強みで、採用期間を従来の3分の1に短縮し、さらには入社後の離職率を20%削減した実績もあるとのこと。
Maki Peopleは3,800万ドルもの資金を調達しており、その革新性と実績が評価されていることがわかります。
Spleenlab(スプリーンラボ)

ドイツのSpleenlabは、半自律型から完全自律型まで、あらゆる種類のモビリティ(移動手段)向けの「AI認識ソフトウェア」を開発しているスタートアップです。
自動運転ドローン、自動車、さらには航空機といった乗り物が、安全に航行できるようにサポートしてくれます。
自動運転の「目」となるAIソフトウェア
Spleenlabの技術は、自動運転システムの「目」や「脳」のような役割を担います。
AIが周囲の環境を正確に認識し、障害物を避け、安全なルートを判断することで、ドローンが荷物を届けたり、自動運転車が街を走ったり、将来的に空飛ぶ車が安全に運行したりすることが可能になります。
私たちの未来の移動を支える存在となりそうですね。
Cognigy(コグニジー)
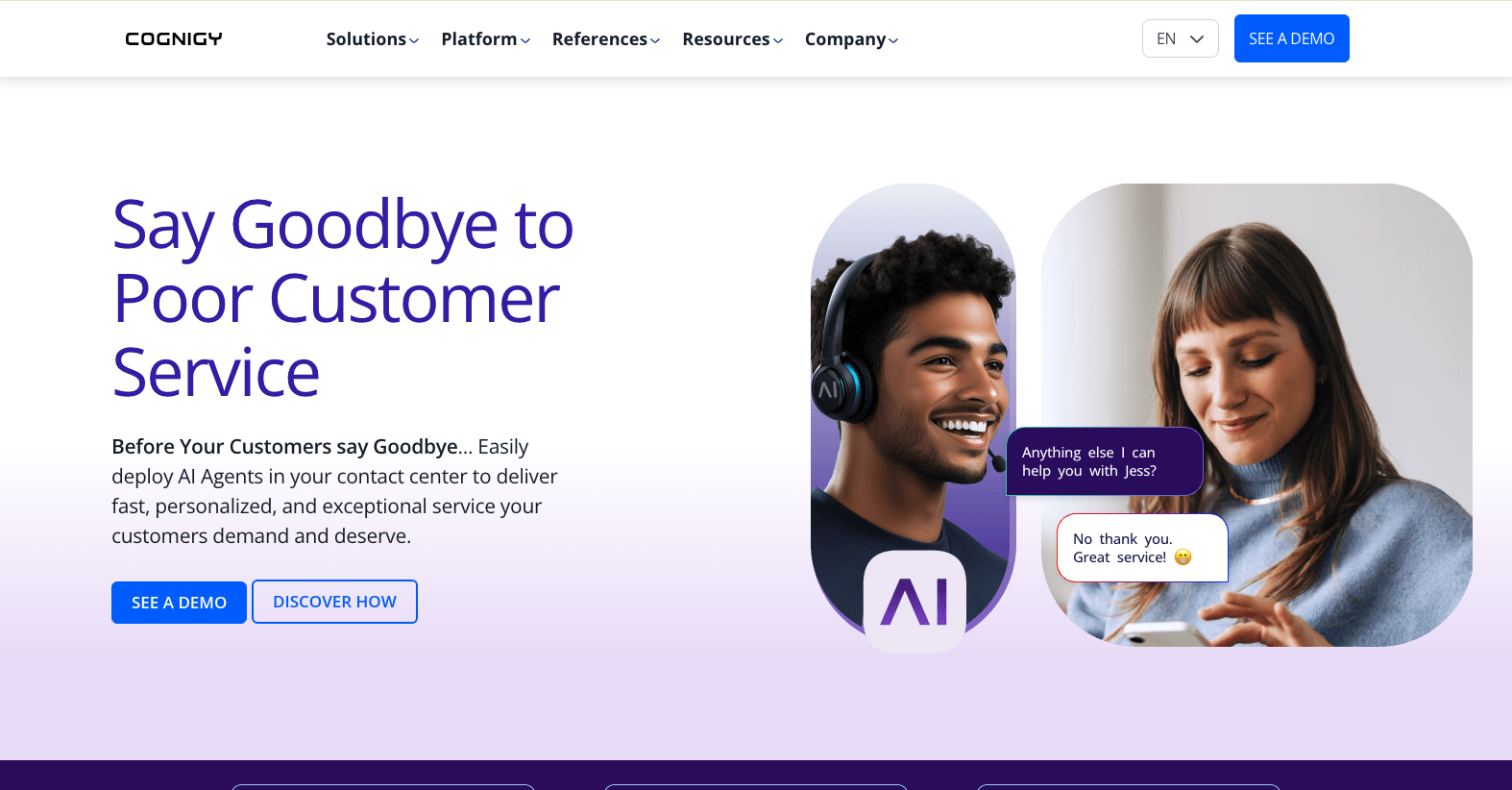
ドイツのCognigyは、企業が顧客サービス向けに高度なAIエージェントを構築・管理できるAIプラットフォームを提供しているスタートアップです。
顧客サポートを賢く自動化するAIプラットフォーム
Cognigyのプラットフォームを使えば、企業はまるで「AIの専門家チーム」を抱えているかのように、自社に合ったAIエージェントを簡単に作ることができます。
このAIエージェントは、会話型AIと生成型AIの技術を組み合わせており、顧客からの大量のリクエストにもスムーズに対応できるのが特徴です。
例えば、よくある質問に即座に答えたり、複雑な問い合わせ内容を理解して適切な部署に振り分けたりと、顧客サポートの質を落とすことなく、大幅な効率化を実現します。
DeepOpinion(ディープオピニオン)
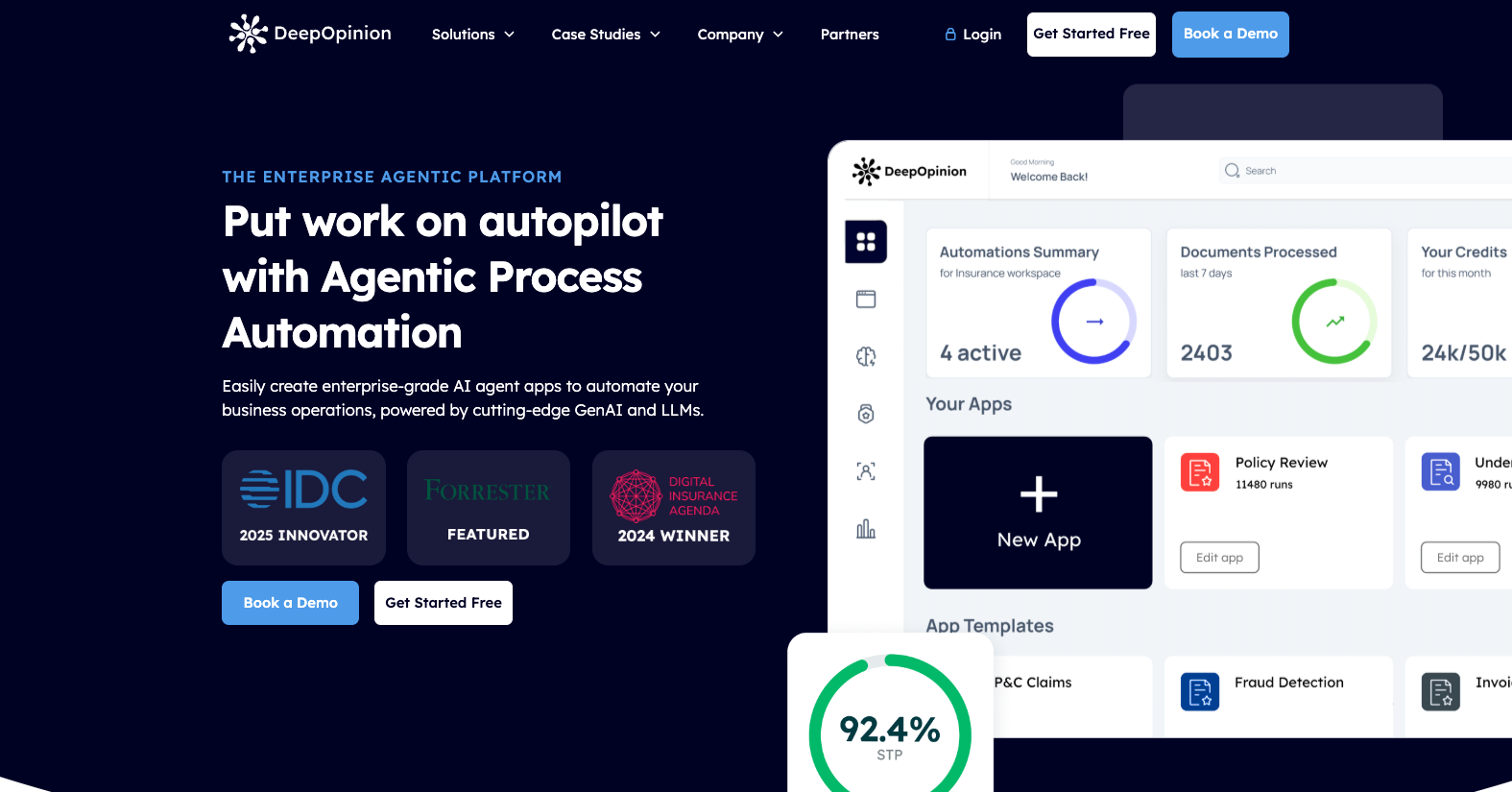
オーストラリアのDeepOpinionは、AIエージェントを活用して、複雑なビジネスプロセスを自動化しているスタートアップです。
彼らのAIは、ただ自動化するだけでなく、学習し、状況の変化に適応していく能力を持っています。
この能力によって、これまで人間の専門知識がなければ難しかった作業も、より効率的かつ効果的に自動化することが可能になります。
専門業務もAIに任せられる時代へ
DeepOpinionのAIエージェントは、与えられたタスクをこなすだけでなく、経験を積むごとに賢くなっていきます。
例えば、契約書の細かな条項をチェックしたり、市場のトレンドを分析して最適な戦略を提案したりと、高度な判断が求められる業務にも対応できるのです。
これは、企業にとって時間とコストの大幅な削減につながるだけでなく、業務の品質向上にも貢献するでしょう。
AIが人間の専門知識を補い、さらに高めてくれるなんて、本当にすごいですね。
Unique(ユニーク)
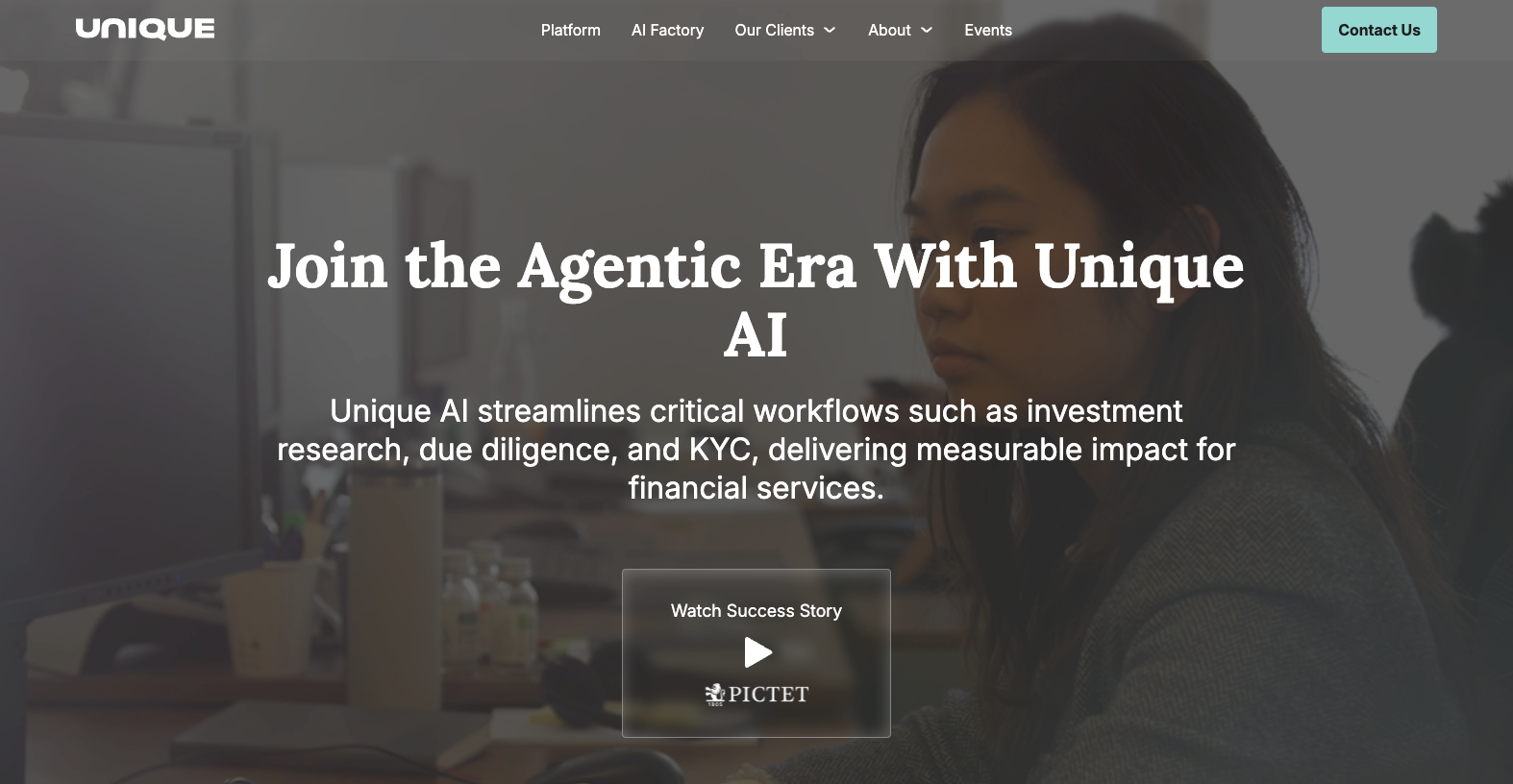
スイスのUniqueは、金融サービス分野に特化したAIエージェントを導入しているスタートアップです。
デューデリジェンス(投資先の調査)や、ポリシー(規定)の要約、ITサポート、さらには契約書の分析といった、専門的で手間のかかるタスクに対応してくれます。
金融業務の「賢いアシスタント」
金融業界の業務は、非常に複雑で専門知識が求められます。
UniqueのAIエージェントは、これらの高度なタスクをAIの力で自動化し、効率化を図ります。
例えば、分厚い契約書の内容を瞬時に解析して重要なポイントを抜き出したり、ITに関する顧客からの問い合わせに自動で対応したりすることで、金融のプロフェッショナルはより戦略的な業務に集中できるようになります。
これは、正確性とスピードが求められる金融業界にとって、非常に強力な味方になりそうですね。
Lovable(ラヴァブル社)「GPT Engineer」
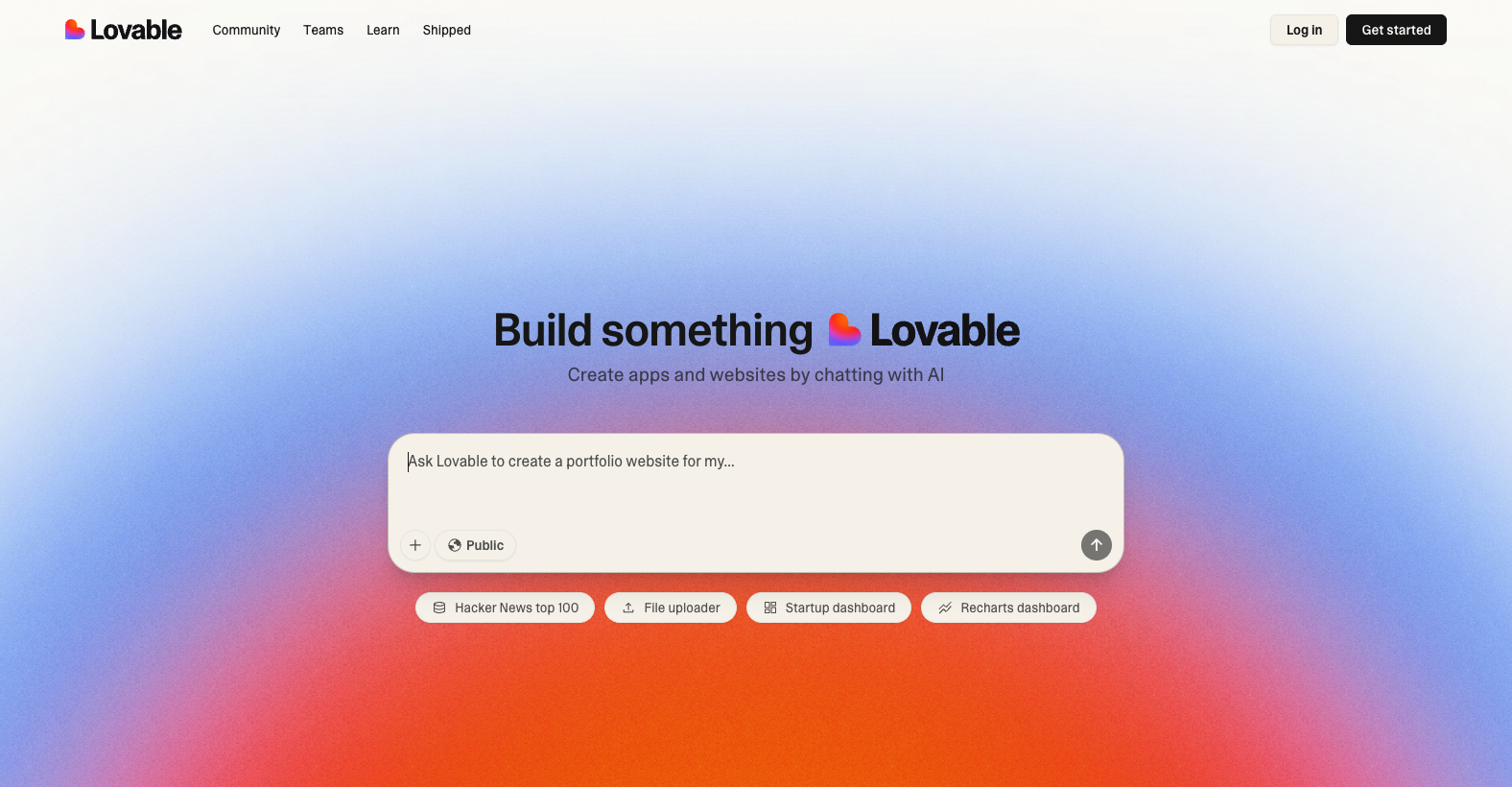
スウェーデンに拠点を置くLovableは、ユーザーが普段の言葉(自然言語)を使って、インタラクティブなウェブ・アプリケーションを作成したり、改良したりできるプラットフォームを構築しているスタートアップです。
彼らの主力製品は「GPT Engineer」と呼ばれています。
「話すだけ」でウェブアプリが作れる革命的なツール
GPT Engineerは、ユーザーが自然言語で「こんなウェブサイトが欲しい」「こんな機能を追加したい」と伝えるだけで、実際に動くコードを生成してくれます。
これにより、プログラミングの専門知識がない人でも、ウェブサイトやウェブ・アプリケーションを簡単に、そしてスピーディーに構築できるようになります。
アイデアを形にするまでのハードルを大きく下げる、まさに革命的なツールですね。
Parloa(パルロア)
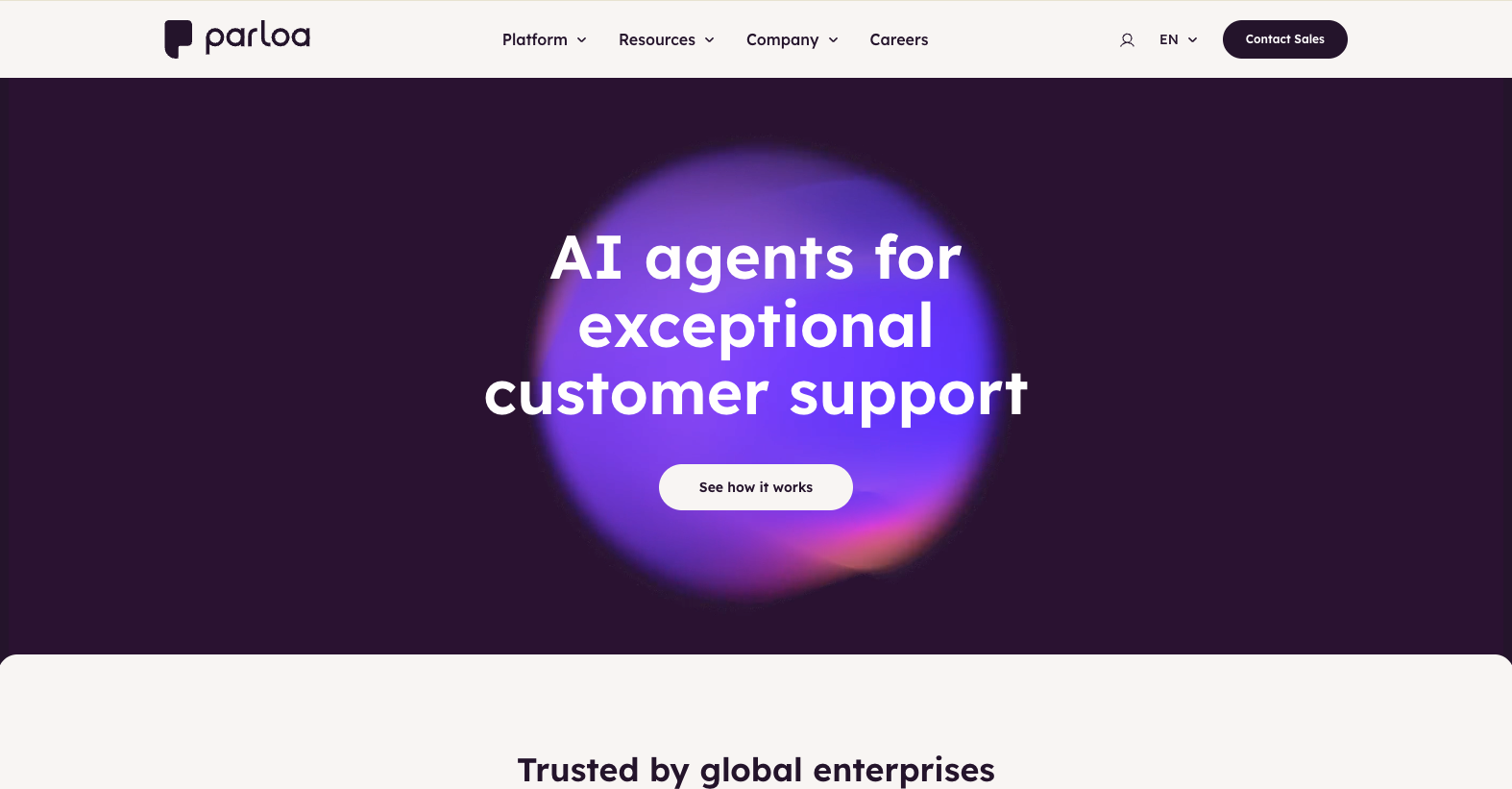
ドイツのParloaは、カスタマーサービス業務のためのAI駆動型音声・チャット自動化プラットフォームを開発しているスタートアップです。
会話型AIと人間のような自然なインタラクション(相互作用)を組み合わせることで、コールセンターの効率を高めることを目指しています。
人間のように話せるAIがコールセンターを変える
Parloaのプラットフォームは、AIエージェントがまるで人間が話しているかのように、非常に自然な音声やチャットで顧客の問い合わせに対応します。
そのため、コールセンターは大量の問い合わせに迅速かつ一貫性のある対応ができるようになり、オペレーターの負担を大幅に減らすことができます。
顧客は待つことなくスムーズに問題を解決でき、企業側もサービス品質を維持しながらコストを削減できる、まさに理想的なソリューションです。
Synthesia(シンセシア)

英国のSynthesiaは、本物そっくりのアバターや声を使って、高品質な合成ビデオコンテンツを生成するAI搭載ツールを開発しているスタートアップです。
AIが作る、まるで本物のような「話す動画」
Synthesiaのツールを使えば、テキストを入力するだけで、本物の人間が話しているかのようなAIアバターが、表情豊かに話す動画を自動で生成してくれます。
企業研修用の教材、マーケティング用のプロモーションビデオ、異なる言語圏向けのコンテンツのローカライゼーション(地域適応)など、その用途は多岐にわたります。
撮影の手間やコストを大幅に削減できるだけでなく、いつでも好きな時に、必要な内容の動画を作成できるのは、コンテンツ制作の常識を覆すほどのインパクトがありますね。
ElevenLabs(イレブンラブズ)

英国と米国に拠点を置くElevenLabsは、超リアルで表現力豊かな音声生成を可能にする、最先端のAI音声合成技術を開発しているスタートアップです。
AIが人の声に命を吹き込む
ElevenLabsの技術は、ただ文字を読み上げるだけでなく、感情やニュアンスを込めた、まるで人間が話しているかのような自然な音声を生成できます。
これは、オーディオブックのナレーション、ゲームのキャラクターボイス、バーチャルアシスタントの声、さらにはポッドキャストの自動生成など、幅広い分野で活用されています。
AIがここまでリアルな声を生成できるとは、本当に驚きです。
2025年1月にはシリーズCラウンドで1億8,000万ドルもの巨額の資金を調達しており、その技術力と市場からの期待の高さが伺えます。
Nevermined
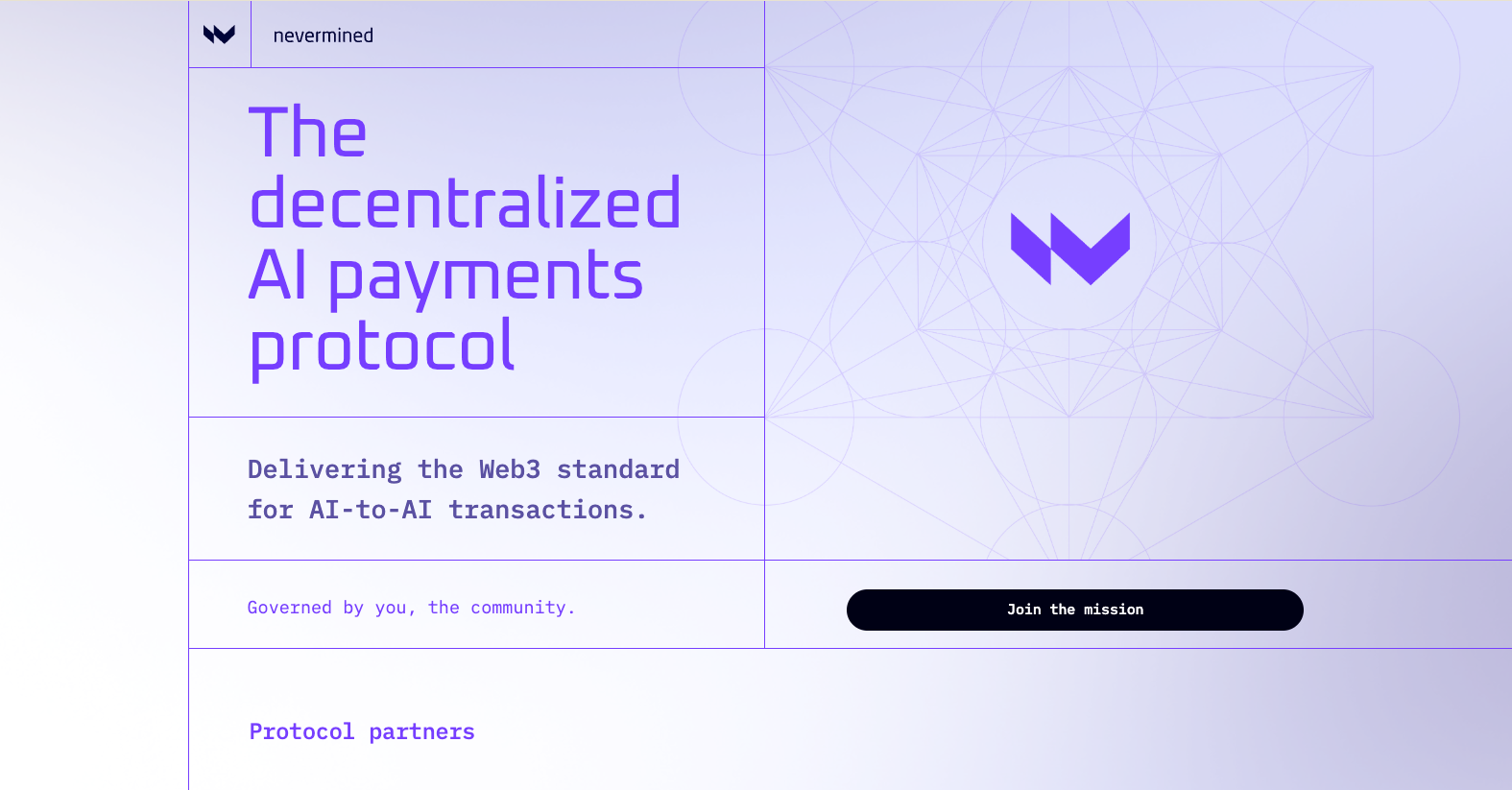
スイスのNeverminedは、「AIのためのPayPal」というユニークなコンセプトを持つスタートアップです。
彼らが提供するのは、分散型AI決済プロトコルで、AIエージェント自身が決済を行えるようにすることを目指しています。
AIエージェントが自ら取引する未来の決済システム
AIエージェントが、人間の介入なしに、自律的に交渉して、その場で料金の支払いまでできたら、とても便利ですよね。
Neverminedの技術は、まさにそれを実現しようとしています。
例えば、あるAIエージェントが別のAIエージェントからデータやサービスを購入する際に、自動で支払いを行う、といったことが可能になります。
AIがますます複雑なタスクをこなし、経済活動に参加していく上で、非常に重要なインフラとなるでしょう。
Juna.ai
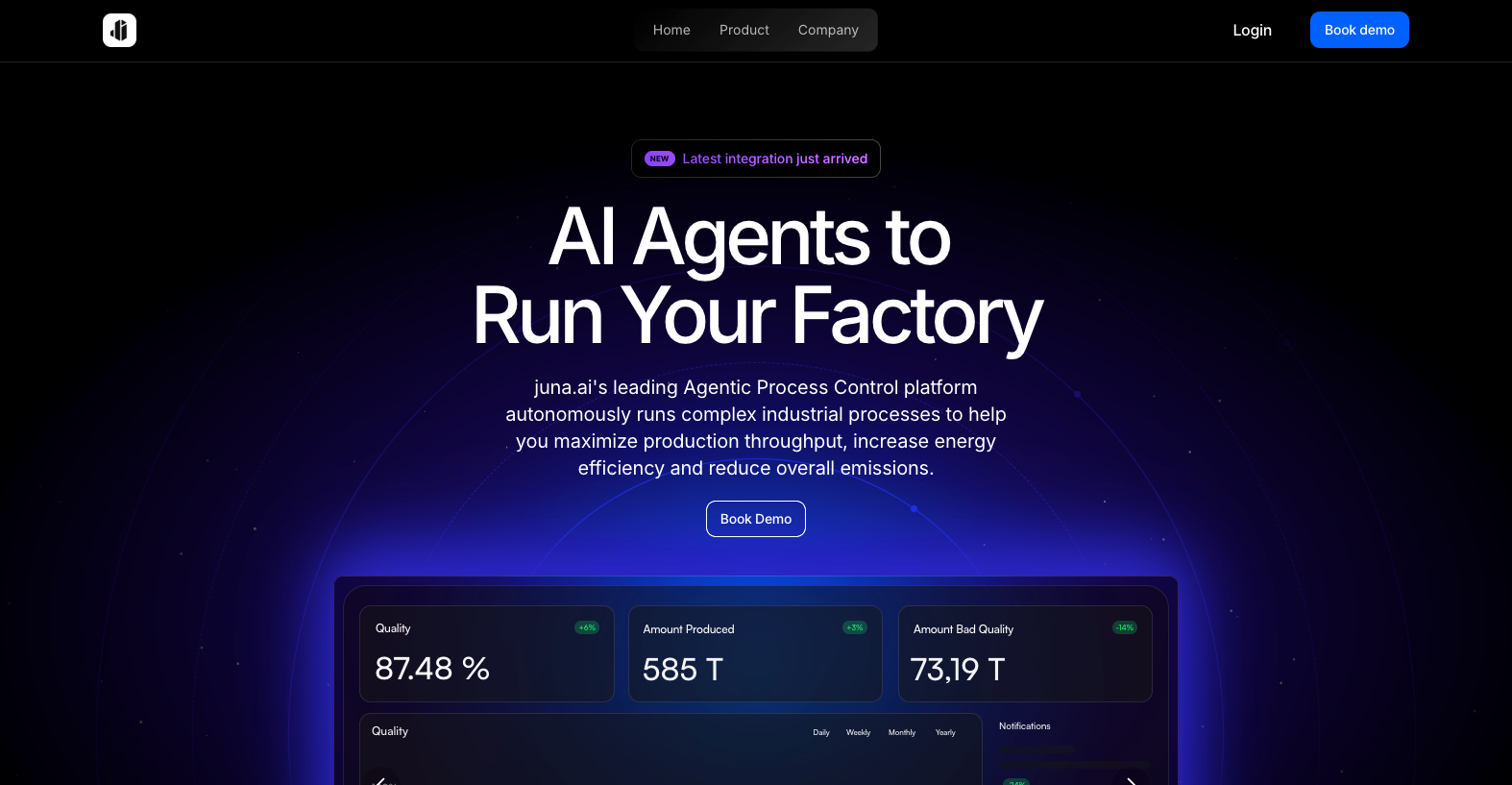
ドイツのJuna.aiは、自律型AIエージェントを使って、産業製造プロセスを最適化することに力を入れているスタートアップです。
工業プラントの管理において、リアルタイムのセンサーデータや過去の生産記録を理解し、迅速な意思決定を行うことで、物理的なプロセスと直接対話するエージェントを導入しています。
工場の頭脳となるAIエージェント
製造業の現場では、常に大量のデータがセンサーから送られてきています。
Juna.aiのAIエージェントは、これらの膨大なデータを瞬時に分析し、工場の稼働状況を最適化するための判断を自動で行ってくれます。
例えば、機械の故障を予測して事前にメンテナンスを指示したり、生産ラインのボトルネック(滞り)を見つけて改善策を提案したりと、まるでAIが熟練の工場長になったような働きをしてくれます。
生産効率が上がり、コスト削減にもつながるのはもちろん、製品の品質向上にも貢献してくれそうです。
GetVocal AI
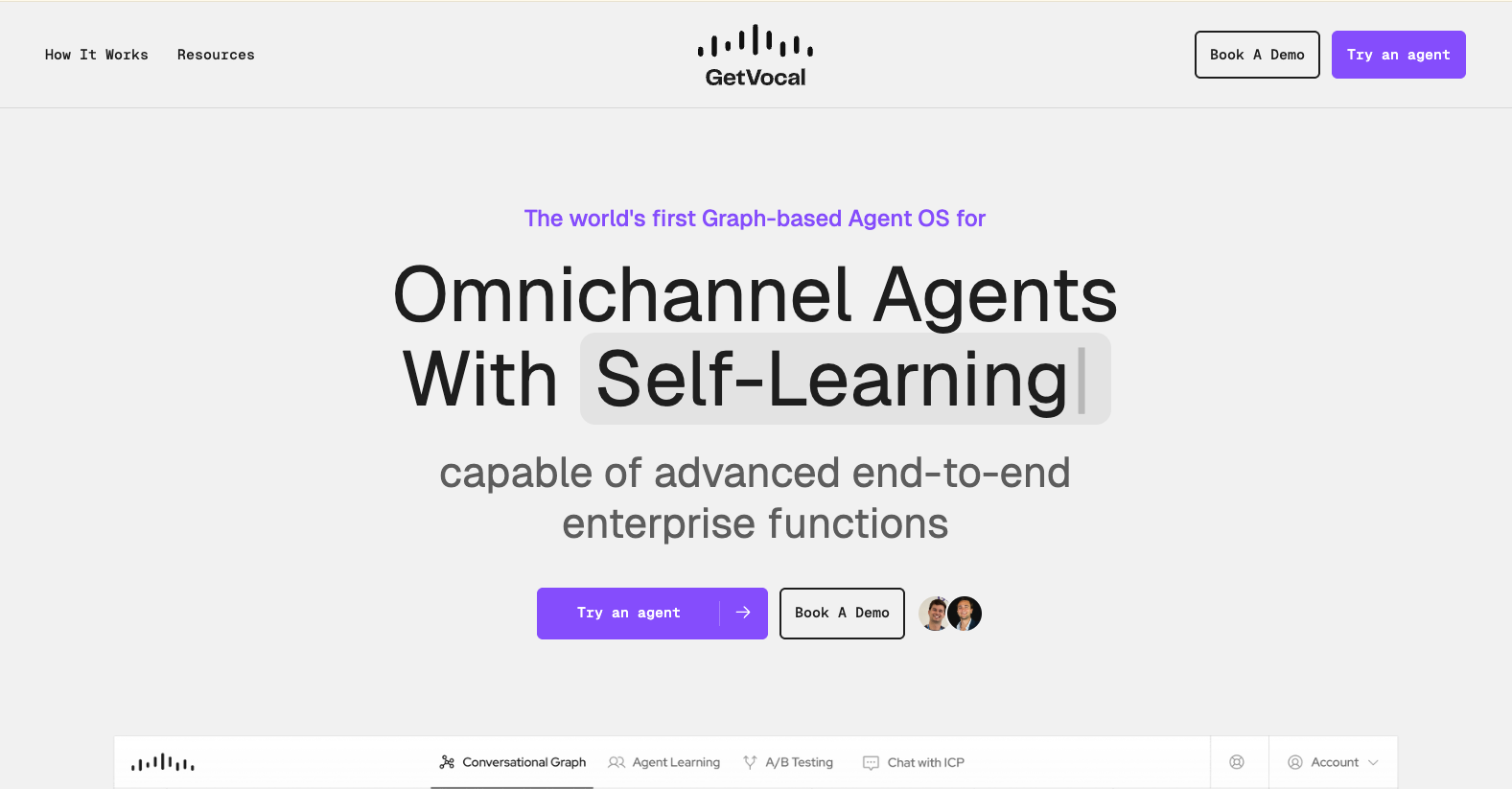
フランスのGetVocal AIは、顧客との接点(カスタマージャーニー)に特化した会話型AIエージェントを提供しているスタートアップです。
企業の内部文書や通話記録、顧客からの問い合わせ履歴(ナレッジベース)を学習する「Conversational Maps(会話マップ)」という独自の技術を基盤としています。
顧客との会話をAIが学習し最適化
企業が顧客とどう関わるかは、ビジネスの成功に直結します。
GetVocal AIのAIエージェントは、顧客がどのような情報に関心を持ち、どのような言葉遣いを好むのかを深く学習し、それに基づいて最適な会話を自動で行ってくれます。
独自の「会話マップ」技術により、まるで顧客の気持ちを先読みしているかのようなスムーズな対応が可能です。
その結果、リード(見込み顧客)獲得数が43%も増加し、週に22時間もの業務時間を削減、さらに顧客との接触コストも79%削減できたという実績があります。
同社は2025年1月には270万ユーロの資金調達を完了しており、その成長性が期待されています。
1.巨額の資金流入とエコシステムの大規模な拡大
米国では数億ドル規模の巨額な資金調達が相次ぎ、中国では政府の後押しと巨大テック企業の投資により「百模大戦」が加速。
欧州でも大型調達が見られ、世界的にAIエージェント市場への大規模な資金流入とエコシステムの拡大が進行。
2.多様な業務領域におけるAIエージェントの専門化と自律化
営業、マーケティング、経理、法務、人事、カスタマーサポート、ソフトウェア開発、セキュリティ、産業製造、そして個人のアシスタントまで、AIエージェントが各業務領域に特化し、特定の複雑なタスクを自律的に実行できるよう進化。
3.大規模言語モデル(LLM)の進化と基盤モデルの多様化
中国勢を中心に、長文処理に強みを持つ「Kimi」や高性能・低コストの「DeepSeek」など、多様な大規模言語モデル(LLM)の競争が激化。
4.マルチモーダルAIエージェントの台頭と応用拡大
マルチモーダルAIエージェントの対等により、リアルな音声生成、合成ビデオコンテンツ作成、AIアバター、さらには物理的な作業を代替するAIロボットなど、表現力と応用範囲が飛躍的に広がる。
5.AIの安全性、信頼性、倫理への高い意識と規制の動き
EU AI Actに代表されるリスクベースの規制整備が各国で加速し、AIシステムの信頼性と社会受容性を確保する動きが顕著。
AIエージェントの技術革新と関連ツール
AIエージェントが、私たちの生活やビジネスにますます深く浸透するにつれて、その能力も目覚ましい進化を遂げています。
まるでSFの世界から飛び出してきたかのように、AIが自律的に考え、行動し、私たちをサポートする姿は、まさに技術革新の賜物と言えるでしょう。
この進化を可能にしているのは、AIエージェントの「脳」とも言える基盤技術の飛躍的な向上に他なりません。
特に注目すべきは、AIが過去の経験を忘れずに学習し続ける「長期記憶」の進化、異なるAIエージェント同士がスムーズに連携するための「共通プロトコル」の確立、そして専門知識がなくても誰もがAIエージェントを開発できるようになる「ノーコード開発ツール」の登場です。
これらの技術がどのようにAIエージェントの可能性を広げ、私たちの未来をどのように形作っていくのか。ここでは、最新の技術動向と、それらを支える具体的なツールについて詳しく見ていきましょう。
AIエージェントの「長期記憶」
AIエージェントが人間のように賢く、そして自然に振る舞うためには、過去の会話や経験を覚えておく「記憶」の機能が欠かせません。
これまで、AIエージェントにはそのセッション中だけの会話を覚える「短期記憶」と、ユーザーの好みや基本情報などを記録する「長期記憶」がありましたが、以前の長期記憶は一度記録されるとあまり柔軟性がなく、状況に合わせた動的な対応が難しいという課題がありました。
記憶を操り、行動を最適化する「LangMem SDK」
しかし、この状況を大きく変えたのが、2025年2月に発表された「LangMem SDK」というツールです。
これは、AIエージェントのフレームワークとして有名なLangChainによって開発されました。
このツールのおかげで、AIエージェントは会話の中から重要な情報を抽出し、それをもとに自分の行動を最適化できるようになりました。
さらに、事実や過去の出来事に関する長期的な記憶をしっかりと保持できるようになったのです。
AIが過去から学び、より賢く行動できるようになるなんて、本当にすごい進化ですね。
また、ラトガース大学、アントグループ、セールスフォースの研究チームは、ドイツの社会学者ルーマンが提唱した「ツェッテルカステン」という効率的なノート取り手法(情報をカードにまとめ、関連付けながら知識を蓄積するやり方)をヒントに、新しい記憶システム「A-MEM」を開発しました。
これは、知識のネットワークを構築することで、より柔軟で文脈(状況)を意識した記憶管理を実現しています。
AIがまるで人間のように知識を結びつけて理解できるなんて、驚きです!
ただし、AIの記憶には課題も存在します。
ただ単に多くの情報を記憶させれば良いというわけではなく、何を記憶させ、何を忘れさせるか、という設計上の判断が非常に重要になってきます。
これは、AIが「賢く忘れる」能力も必要とされるという、興味深い課題ですね。
AIエージェント間の共通プロトコル「MCP」
AIエージェントが様々なタスクをこなすには、複数のAIエージェント同士が協力したり、外部のサービスやデータと連携したりする必要があります。
その連携をスムーズにするために登場したのが、「MCP(Model Context Protocol)」というAIエージェント間の共通プロトコル(通信規約)です。
AIエージェント同士がスムーズに「会話」する仕組み
MCPが登場したことで、異なるAIエージェントやシステムの間でも、まるで共通の言語を話すかのように、簡単に情報交換や連携ができるようになりました。
これにより、AIエージェントがより複雑なタスクを分担して実行したり、他のAIサービスと協力してより高度なソリューションを提供したりすることが容易になります。
例えば、CData Softwareは、400種類を超えるAPI(アプリケーションと外部サービスをつなぐインターフェース)に対応したMCP Serverの実装である「CData MCP Servers」の無償ベータ版をリリースしました。
これにより、Salesforce、Jira、kintoneといったビジネスでよく使われるSaaS(ソフトウェア・アズ・ア・サービス)や、様々なデータベースへ、AIエージェントが安全に双方向で接続できるようになりました。
このMCPの技術によって、AIエージェントは、これらのサービスやデータベースに保存されているデータを、表形式のSQLベースのモデルに変換して操作できるようになります。
つまり、データの探索、情報の検索(クエリ実行)、データの書き込み、更新、削除、さらにはデータベースの複雑な処理(ストアドプロシージャの実行)まで、人間が直接操作するのと同じように、AIエージェントが自律的に行えるようになるのです。
ノーコード開発ツール
AIエージェントの構築と運用は、これまではプログラミングの知識を持つ専門家でなければ難しいとされていました。
しかし、最近では複雑なコーディングを一切必要とせず、まるでブロックを組み立てるようにAIエージェントを作り上げられる「ノーコード開発ツール」が続々と登場しています。
これにより、ITの専門家でなくても、誰もが手軽にAIエージェントをビジネスに導入できるようになり、その活用範囲は大きく広がっています。
Allganize「Agent Builder」
AIエージェントを企業で活用する際に、最も気になるのが「セキュリティ」ではないでしょうか。
Allganizeが提供する「Agent Builder」は、このセキュリティ面に徹底的に配慮しながら、企業がAIエージェントをノーコードで簡単に構築・運用できる機能を提供しています。
AIエージェントを安全に構築・運用
Agent Builderの最大の特長は、外部ネットワークの制限やデータアクセス制限を行うことで、AIエージェントの実行環境を完全に分離できる点です。
これにより、企業の重要な情報資産が外部に漏れるリスクを最小限に抑え、安心してAIエージェントを利用できます。
さらに、企業が自社サーバー内でシステムを運用する「オンプレミス環境」にも対応しているため、より厳格なセキュリティ要件を持つ企業でも導入しやすいのは大きなメリットです。
DNPとBIPROGYのツール
大日本印刷(DNP)とBIPROGY(ビプロジー)が共同で開発しているのは、AIエージェントを搭載したアバターを、なんとノーコードで開発・運用できるツールです。
AIアバターがどこでも活躍!
このツールを使えば、ウェブサイト上で顧客対応を行うAIアバターはもちろんのこと、店舗のデジタルサイネージや、話題のメタバース空間といった様々な場所で、AIエージェント機能を備えたアバターを専門知識なしに配信できるようになります。
AIの「顔」を簡単に作れそうで、企業の情報発信がもっと楽しくなりそうです。
株式会社ノーコード総合研究所の支援
株式会社ノーコード総合研究所は、特に中小企業が抱える「人手不足」や「業務の属人化」(特定の業務が特定の社員にしかできない状態)といった共通の課題に対し、自律的に行動・学習し続けるAIエージェントの開発をノーコードで支援しています。
中小企業の課題をAIが解決
この支援によって、中小企業は様々な業務の自動化を実現できます。
例えば、紙の帳票からの手入力作業をAIが自動化したり、請求書や見積書をAIが自動生成したり、さらには社内マニュアルに基づいた質問応答チャットボットや、多言語対応のチャットボットなども簡単に作れるようになります。
そうなれば、これまで人手に頼っていた定型業務から解放され、社員はより創造的で価値の高い仕事に集中できるようになります。
AIエージェントが切り拓く新たな可能性:多岐にわたる活用分野
AIエージェントの技術革新は、様々な業界や業務に新たな可能性をもたらしています。
彼らはもはや単なる自動化ツールではなく、人間のように状況を判断し、自律的にタスクを遂行することで、人件費や外注費の削減、業務効率の大幅な向上、そして生産性の飛躍的な向上に貢献する存在へと進化しています。
ここでは、AIエージェントがどのようにしてビジネスの現場を変革しているのか、具体的な活用分野とそれに特化した企業の動向を見ていきましょう。ソフトウェア開発から営業、カスタマーサービス、採用、医療、物流、セキュリティ、さらにはマルチモーダルな領域まで、AIエージェントの活躍の場は広がる一方です。
エンジニア・開発組織向け
ソフトウェア開発の現場では、コードを書くだけでなく、テストやインフラの準備、品質管理、さらには過去の技術的な負債の解消など、非常に多くのタスクが発生します。
AIエージェントは、これらのソフトウェア開発ライフサイクル全体のワークフローを強力にサポートし、エンジニアの負担を軽減してくれます。
開発業務をスマートにするAIアシスタント
AIエージェントは、コードの自動生成を支援したり、開発したソフトウェアが正しく動くかどうかのエンドツーエンドテストを自動で行ったり、サーバーなどのインフラを自動で準備したりと、開発プロセスを全体的に効率化します。
以前ご紹介したCognitionの「Devin」が、まさにこの分野で注目されているAIソフトウェアエンジニアの代表例です。
営業・マーケティング向け
営業やマーケティングの分野では、いかに効率的に見込み顧客を見つけ、顧客に響くメッセージを届け、最終的な売上につなげるかが重要です。
AIエージェントは、これらの収益最大化を目指す活動を強力に支援してくれます。
収益アップに貢献するAI営業・マーケティング
AIエージェントは、見込み顧客の獲得プロセスを自動化したり、顧客一人ひとりに合わせたパーソナライズされたコンテンツ(例えば、メールや広告文)を自動で作成・配信したり、過去のデータから将来の売上を予測・分析したりといったことが可能です。
Artisanの「Ava」や、11xの「Alice」といったAIエージェントが、この分野で営業活動を劇的に効率化する代表例として活躍しています。
カスタマーサービス向け
顧客サポートは、企業の顔となる重要な業務ですが、24時間365日の対応や多言語サポート、即時応答など、多くの課題を抱えています。
AIエージェントは、これらの課題を解決し、顧客対応の質を向上させながら、人材の採用・研修・維持にかかる負荷を軽減してくれます。
24時間稼働!AIが顧客を笑顔に
AIエージェントは、時間や言語の壁を越えて、顧客からの問い合わせに即座に対応できるので、顧客はいつでも必要な情報を得られ、企業は人件費を抑えながら質の高いサポートを提供できます。
これまでにご紹介したDecagon、Cognigy、Parloaなどが、この分野の主要なプレーヤーとして活躍しています。
また、トゥモロー・ネットは、複数のAIエージェントが連携して複雑な問い合わせを自動化する「CAT.AI マルチAIエージェント」を提供しています。
これは、情報収集、状況判断、そして最適な応答といった一連のプロセスを複数のAIエージェントが分担して並行処理することで、より幅広い質問に的確に回答し、業務効率化をさらに促進します。
リクルーティング(採用)向け
人材採用の現場では、求人票の作成から候補者の探索、スカウトメールの送信、面接日程の調整、そして面接後のフォローアップまで、非常に多くのアナログ業務が存在します。
AIエージェントは、これらの業務を自動化し、さらに評価基準の標準化や評価の一貫性を確保することで、より効率的で公平な採用活動をサポートします。
AIが最適な人材を見つける
AIエージェントは、大量の履歴書や候補者データの中から、企業が必要とするスキルや経験を持つ人材を効率的に見つけ出したり、候補者に合わせたスカウトメールを自動で作成・送信したりと、採用担当者の手間を大幅に削減します。
さらに、面接のスケジュール調整や、候補者への自動フォローアップまで行ってくれます。
前述のMaki PeopleやMercorが、この分野で採用活動を革新している代表的な企業です。
AIが採用を効率化してくれるなんて、本当に助かりますね。
法務・コンプライアンス向け
法務やコンプライアンス(法令遵守)の分野は、膨大な法律文書や法令、判例データの中から正確な情報を判断する必要があり、AIエージェントとの相性が非常に良いとされています。
AIが企業の「法の番人」に
AIエージェントは、法務リサーチの自動化、契約書の内容チェック(レビュー)、訴訟戦略の立案サポート、さらにはクライアントとのコミュニケーション支援など、高度な法務業務で活躍が期待されます。
Genie AIや、前述のUniqueが、この分野で革新的なサービスを提供しています。
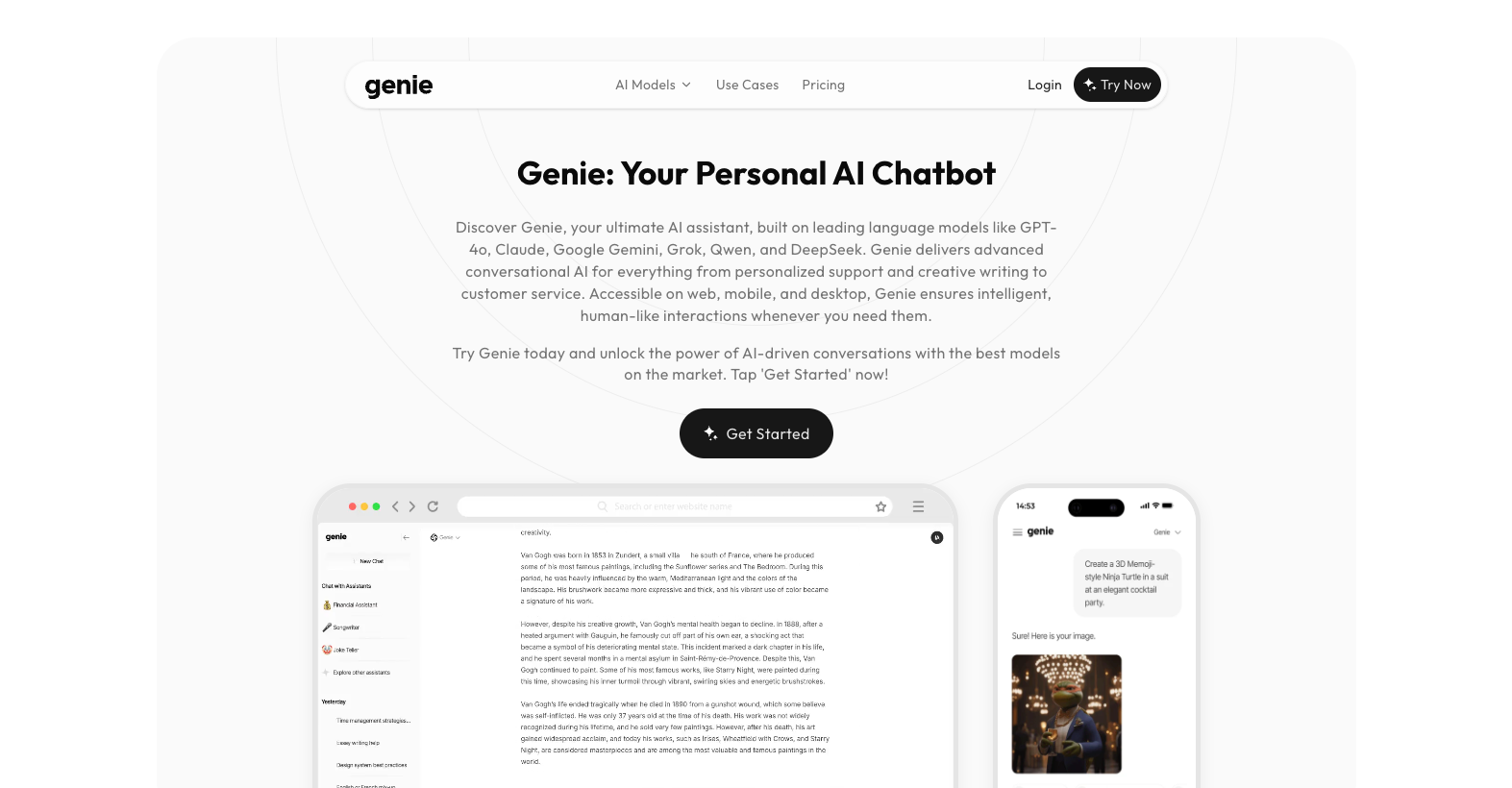
さらに、英国のHorizingは、コンプライアンスのためのAIエージェント構築に注力しており、特に法規制の変更がビジネスに与える影響を迅速に理解することに重点を置いています。
AIが常に最新の法規制を把握し、ビジネスへの影響を教えてくれるなんて、企業経営者にとって非常に心強いですね。
ヘルスケア向け
医療分野では、医療費請求管理、診断支援、カルテ記入の自動化など、医療従事者の負担が大きい業務が数多く存在します。
AIエージェントは、これらの業務を支援することで、医療現場の効率化と、より質の高い医療提供に貢献します。
医療現場をAIが支援する
AIエージェントは、患者の医療費請求を自動で管理したり、医師の診断をサポートするために膨大な医療データから関連情報を提示したり、診察内容を自動でカルテに記入したりと、医療従事者の時間と労力を節約してくれます。
Qualcomm AI Program for Innovator 2025に選出されたModAsteraは、医療AIエンジニアリングエージェントを提供しており、AI開発期間を数ヶ月からわずか数日に短縮することを目指しています。
また、Biorithmは、デジタルヘルス、高度センサー、データサイエンスを組み合わせ、母子保健の向上を目指しています。
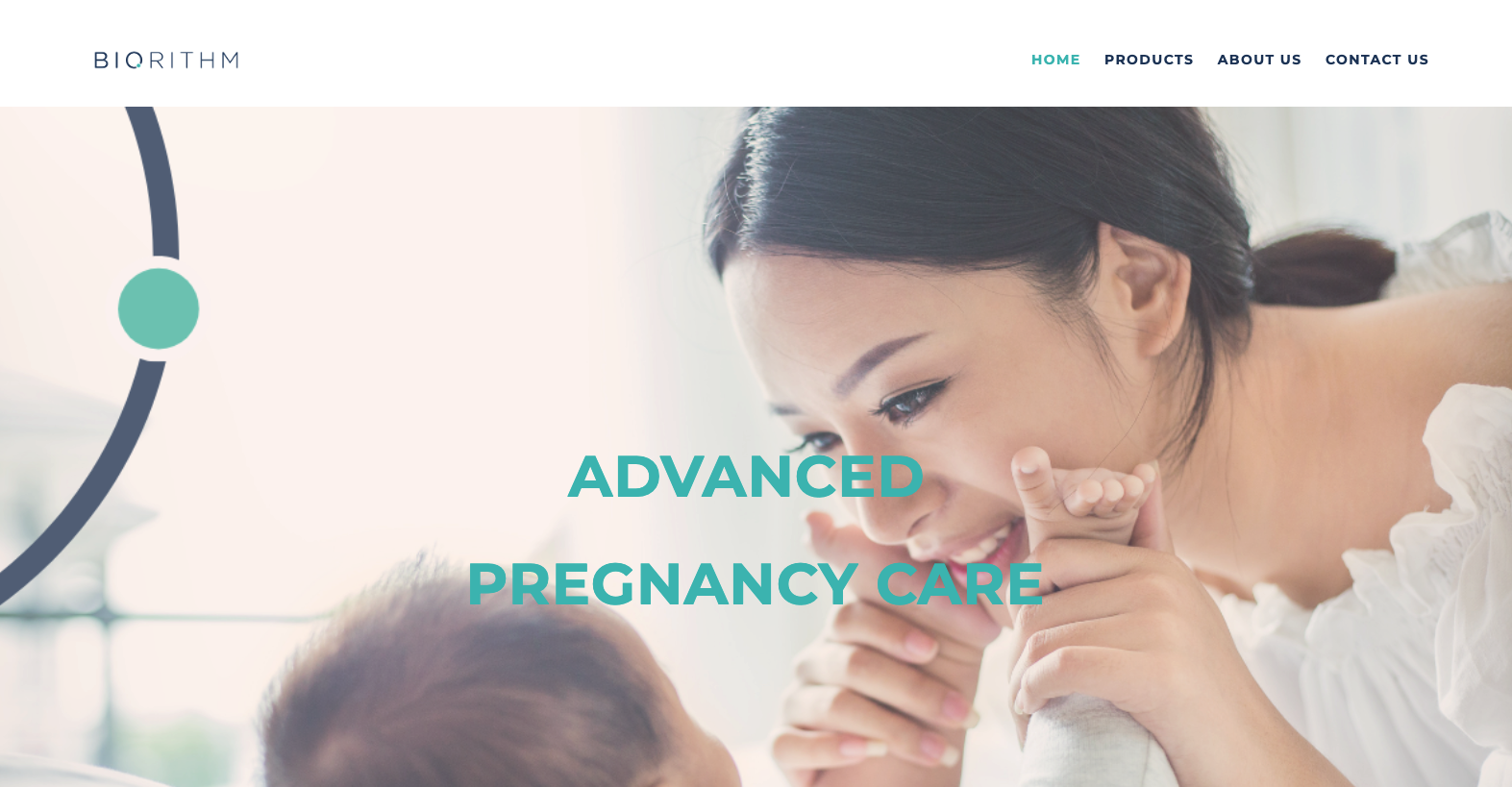
物流・サプライチェーン管理向け
物流やサプライチェーン管理の分野では、見積依頼、請求書照合、進捗確認、サプライヤーとのやり取り、決済など、反復的かつ大量の書類のやり取りが発生するバックオフィス業務が非常に多いのが特徴です。
AIエージェントは、これらの業務の自動化を強力に推進します。
AIが物流の裏側をスムーズに
AIエージェントは、受け取った見積書と請求書の内容を自動で照合したり、発注した商品の進捗状況をサプライヤーに問い合わせて確認したり、支払い処理を自動で行ったりと、一連のバックオフィス業務を効率化します。
そのため、人為的なミスを減らし、業務スピードを向上させることが期待できます。
サプライチェーン全体の流れがAIによってスムーズになるのは、企業にとって大きなメリットですね。
セキュリティ・リスク管理向け
AIエージェントの活用が広がるにつれて、そのセキュリティとリスク管理の重要性も高まっています。
IBM X-Force脅威インテリジェンス・インデックス2025では、AIエージェントを構築するフレームワークにおいて、リモートコード実行の脆弱性(セキュリティ上の弱点)のような問題が今後さらに頻繁に発生する可能性があると指摘されています。
AIを守るセキュリティ
2025年にはAIの導入がさらに進むにつれて、AIそのものを標的とした専用の攻撃ツールキットが開発される動機も高まると警告されており、企業はAIシステムが狙われるリスクに対して、これまで以上に警戒を強める必要があります。
そのため、企業はAIパイプライン、つまりAIのデータ収集から開発、運用に至るまでの一連の流れを、セキュリティの観点からしっかりと保護することが不可欠です。
AIを安全に活用するためには、AIのセキュリティ対策もAI自身と同じくらい重要だということですね。
マルチモーダルAIエージェント
AIエージェントの最先端技術の一つが、「マルチモーダルAIエージェント」です。
これは、テキスト、音声、画像、動画、センサー情報など、異なる形式のインプット(入力情報)を同時に処理し、それらを総合的に理解することで、より高度な判断やアウトプット(出力情報)を可能にするAIです。
多様な情報を理解し、行動するAI
人間が目や耳、その他の五感を使って世界を認識するように、AIも複数の情報源から情報を得ることで、より複雑で現実世界に近いタスクをこなせるようになります。
音声領域におけるマルチモーダルAIエージェントは、主にカスタマーサービスやセールス対応といった、顧客との「会話」が中心となるユースケースで活躍しています。
特に、企業が複数の部署で既存のシステムと連携しながら、電話の受電や架電をAIが自動で行う「エンタープライズ向けAI電話」の分野が盛んです。
例えば、前述したElevenLabsなどが、開発者向けの高性能な音声生成ツールを提供しています。
また、日本の名古屋大学が開発した日本語特化のリアルタイム音声対話モデル「J-Moshi」は、会話中の相槌の打ち方や、相手と同時に話し始める「発話のオーバーラップ」が非常に自然で、大きな注目を集めています。
まるで人間と話しているかのようなAIの登場は、コミュニケーションの未来を大きく変えるでしょう。

動画や画像領域のマルチモーダルAIエージェントは、自然言語処理と取り込んだ画像情報を組み合わせて、AIが「アバター」を作成して会話したり、プロフェッショナルな動画として出力したりするサービスが成長しています。
これらは、マーケティング、カスタマーサポート、社内トレーニングなど、視覚的な情報伝達が重要な場面で活用されています。
Fotographer AIは、わずか1枚の画像から多視点・多様なシーンを高解像度で生成できる画像生成AI制御ツールキット「ZenCtrl」をオープンソースとして公開しました。
これは、クリエイティブな表現の可能性を大きく広げてくれる、素晴らしいツールですね。
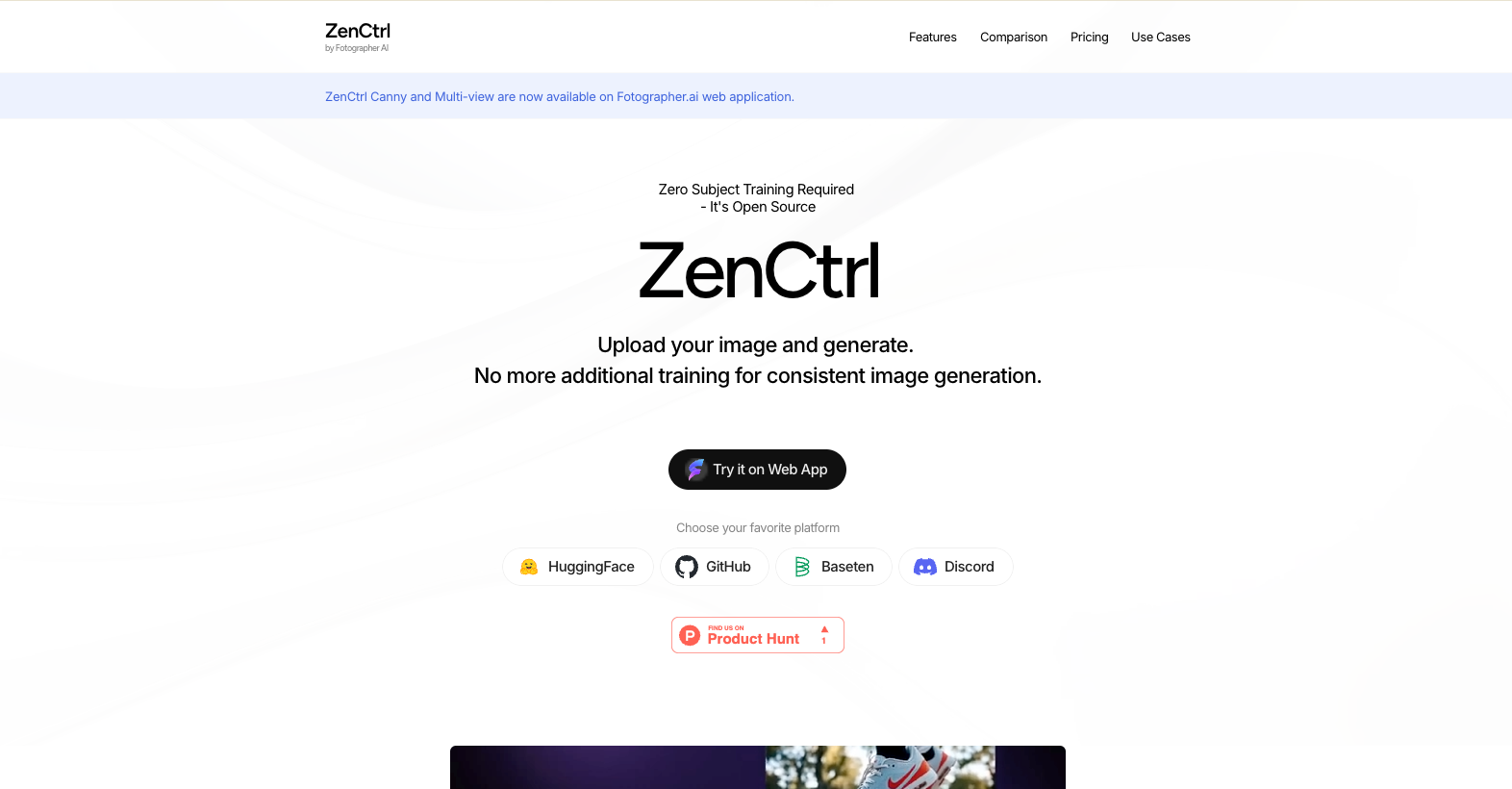
物理的な作業の代替や、多様なデータでの判断・実行が求められるAIロボットは、マルチモーダルAIとの相性が非常に良いため注目を集めています。
ヒューマノイドロボットの開発とAIをセットで進めるFigure AIのようなスタートアップや、倉庫や工場のような物理的な反復作業が多いユースケースに特化したスタートアップが登場しています。
Qualcomm AI Program for Innovator 2025に選出されたAMATAMAは、次世代ヒューマノイドテクノロジーを実現するプラットフォームの開発に注力しています。
AIロボットが私たちの生活や労働現場で活躍する未来は、もうすぐそこまで来ていそうですね。
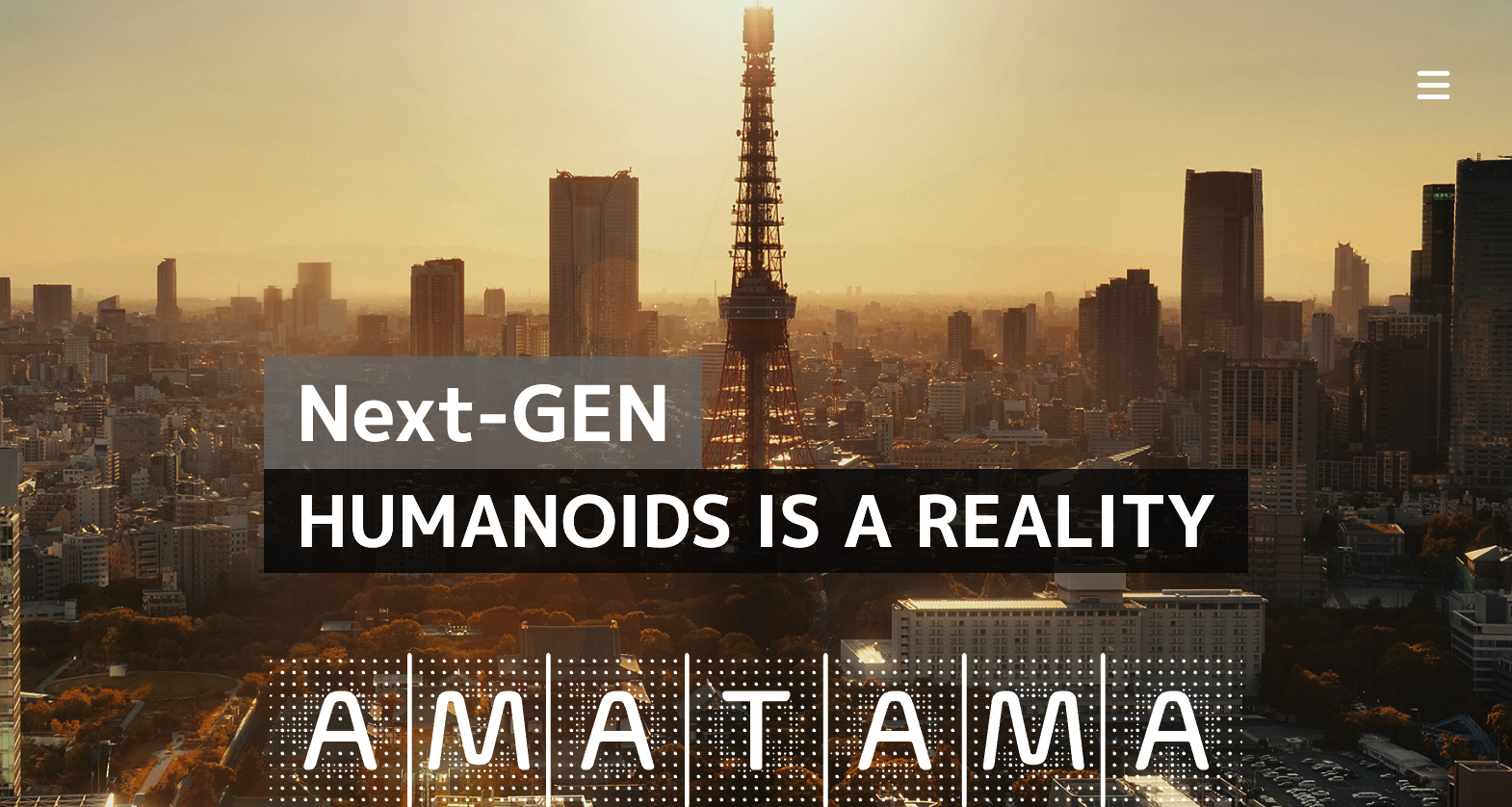
AIエージェント市場はまだ黎明期にあり、特定の領域や一部のスタートアップが急速に成長・資金調達を重ねている状況です。
1.AIエージェントの機能向上と汎用性の拡大
長期記憶技術(LangMem SDKなど)やAIエージェント間の共通プロトコル(MCP)の進化により、AIエージェントの機能が向上。
これにより、ソフトウェア開発から営業、カスタマーサービス、採用、法務、医療、物流、セキュリティまで、多様な業務分野での活用が加速。
2.業務効率化と生産性への貢献
各分野において、コード生成、リード獲得自動化、24時間顧客対応、面接日程調整、法務リサーチ、医療費請求管理など、ルーティン業務の自動化と人的負担の軽減を通じて、企業全体の生産性向上に寄与。
3.ノーコード開発による導入促進
複雑なコーディングを必要としないノーコード開発ツールが登場し、専門知識がない企業でもAIエージェントを容易に構築・運用できるように。
4.マルチモーダルAIの進化と応用拡大
マルチモーダルAIエージェントが台頭によって、音声対話モデルの自然性向上や、合成ビデオ生成、AIロボットによる物理作業代替など、AIの表現力と実世界での応用範囲が大きく広がる。
5.セキュリティと信頼性確保の重要性
AIエージェントの活用が広がるにつれて、セキュリティリスクが増加。
これに対応するため、AIパイプライン全体の保護や、国際的な規制(EU AI Actなど)への適合が喫緊の課題として認識されている。
日本におけるAIエージェント関連スタートアップの動向
ここからは、私たちにとってより身近な日本のAIエージェント関連スタートアップの動向に焦点を当てていきましょう。
日本市場におけるAIエージェント関連スタートアップの資金調達規模は、米国や中国といった他国と比較するとまだ小さい傾向にあります。
しかし、少子高齢化に伴う労働力不足など、国内独自の社会課題の解決に焦点を当てた、実用的なAIエージェント技術の進化が見られます。
政府によるAI開発支援やデジタルトランスフォーメーション(DX)推進策も、関連技術への投資や開発を促進しています。
また、日本市場では、独立したAIエージェント専門のスタートアップが大型調達を繰り返すというよりも、むしろ大企業が自社のサービスに応用としてエージェント機能を開発したり、スタートアップと連携したりする形での進展が目立つ傾向にあります。
これは、日本の産業構造や企業の特性を反映した、独自の進化と言えるかもしれません。
それでも、AIエージェントへの期待は非常に高く、日経クロステックが発表した「テクノロジー未来投資指数」では、「AIエージェント」が総合1位にランクインするなど、その注目度の高さが伺えます。資金流入の勢いも著しく、2024年には30億ドル以上がこの分野に投じられたと見られており、今後さらなる発展が期待されます。
以下に、日本のAIエージェント関連の具体的なスタートアップとその取り組みを挙げていきます。
Sakana AI
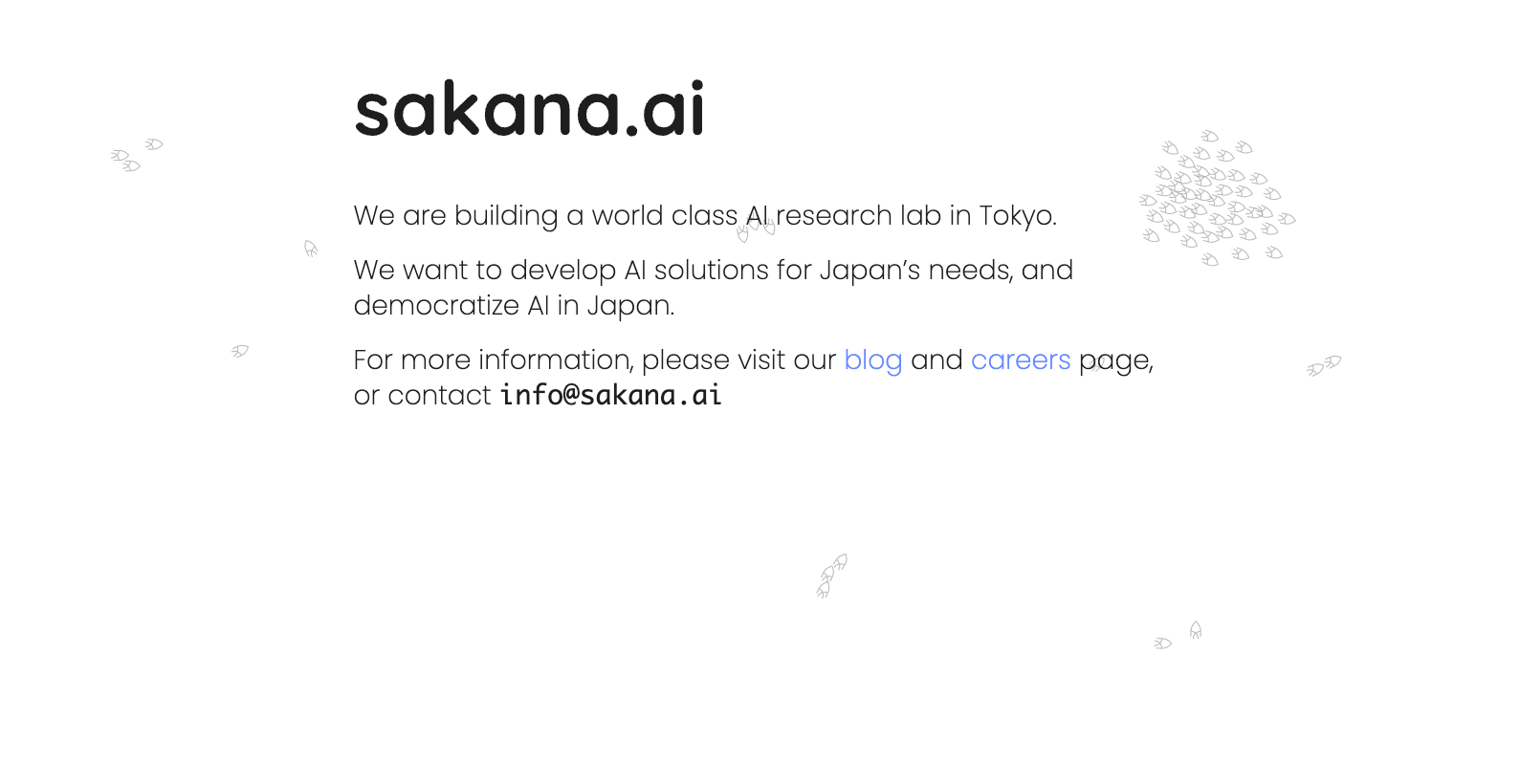
Sakana AI(サカナAI)は、大規模言語モデル(LLM)エージェントの集団を生み出す新しい技術「CycleQD」を開発し、国内外から大きな注目を集めている日本のスタートアップです。
AIが「群れ」で賢くなる新技術
Sakana AIの「CycleQD」は、まるで魚の群れのように、複数のAIエージェントが連携し、お互いに学び合いながら、一つの大きな目標を達成するようなイメージです。
個々のAIエージェントが持つ能力を組み合わせることで、単独では解決できないような複雑な課題にも対応できるようになります。
これは、AIの協調性を引き出し、より高度な知能を実現する画期的な技術と言えるでしょう。
同社は2024年1月にシリーズAラウンドで3,000万ドル(約45億円)という国内では特筆すべき大型資金調達を完了し、すでにユニコーン企業(評価額が10億ドルを超える未上場企業)となるなど、その成長性への期待は計り知れません。
NTT、KDDI、ソニーグループといった国内の大手企業からも出資を受けており、日本のAI分野における「希望の星」として大きな注目を集めています。
Zaimo.ai

Zaimo株式会社は、経営管理業務をAIの力でスマートにするAIエージェントZaimo.ai(ザイモ・エーアイ)を提供しているスタートアップです。
事業計画の作成、予算と実績の管理(予実管理)、そして社内の情報共有といった、経営に欠かせない業務をAIが簡素化してくれます。
経営をAIが「見える化」する
経営者にとって、事業の状況を正確に把握し、未来の計画を立てることは非常に重要ですが、多くの時間と労力がかかります。
Zaimo.aiは、これらの経営管理業務を自動化し、データを分かりやすく整理してくれるため、経営者はより迅速かつ的確な意思決定ができるようになります。
例えば、過去の売上データから今後の事業計画を自動で提案したり、予算と実績のズレを瞬時に分析して原因を教えてくれたりするでしょう。
AIによって経営が「見える化」されるのは、本当に心強いですね。
同社はシードラウンドで約1億円を調達しており、日本のスタートアップとして今後の成長が期待されます。
VARIETAS
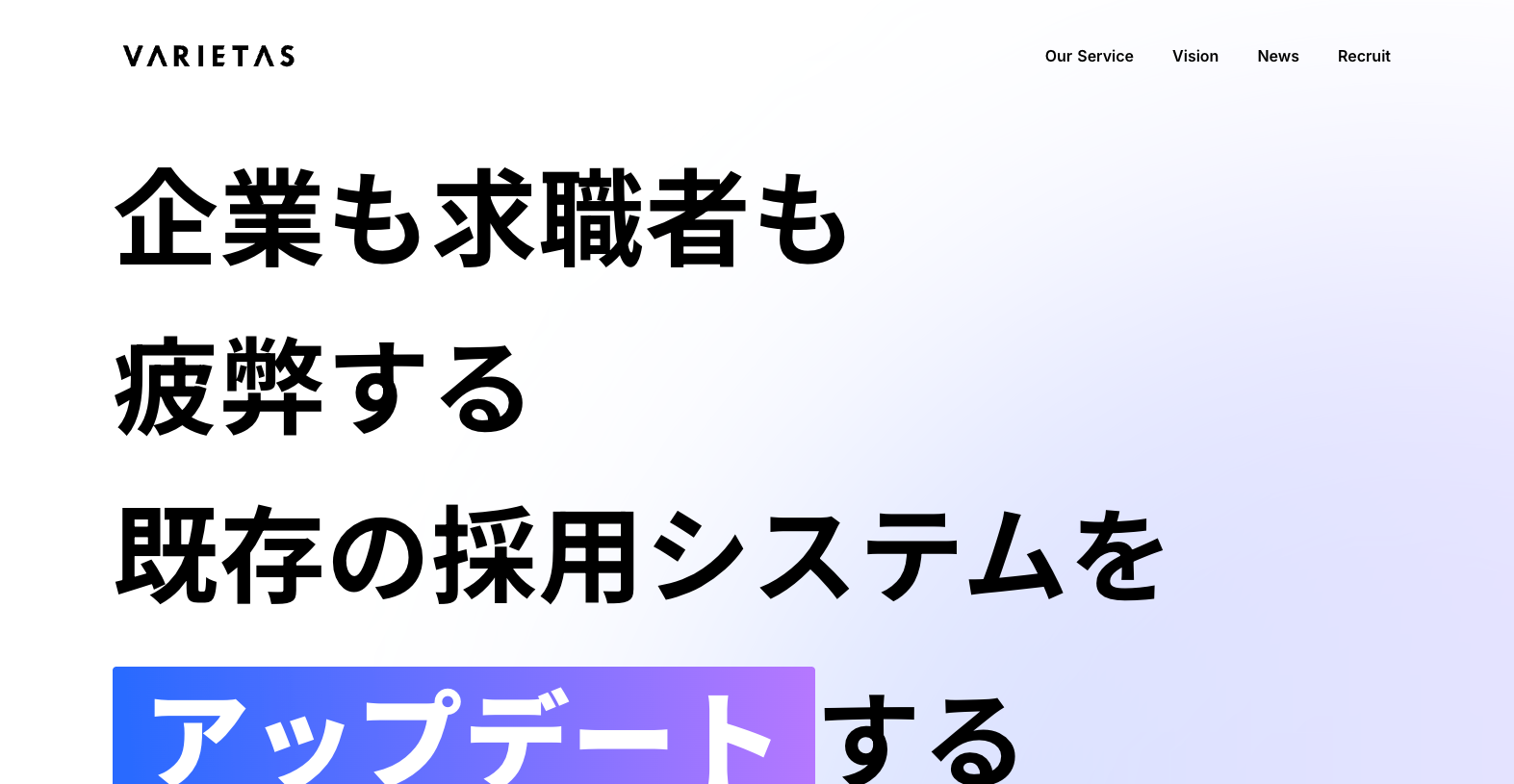
VARIETAS(ヴァリエタス)は、採用活動における書類選考や一次面接を、AI面接官エージェントが新しい仕組みと技術で代わりに行い、社会全体の生産性向上を目指しているスタートアップです。
AI面接官が採用プロセスを革新
採用活動は、企業にとって重要な一方で、多くの時間と労力がかかる業務です。
VARIETASが開発するAI面接官エージェントは、応募書類の選考から一次面接までをAIが担当することで、採用担当者の負担を大幅に軽減します。
AIが公平な基準で候補者を評価するため、選考プロセスの効率化だけでなく、採用における無意識の偏りを減らし、より多様な人材を発掘できる可能性も秘めています。
これは、企業にとっても求職者にとっても、よりスムーズで公平な採用活動を実現してくれそうな、期待できる取り組みですね。
同社はシリーズAで6億円を調達しており、その技術とビジネスモデルが評価されていることがわかります。
AGEST

AGEST(エイジスト)は、ソフトウェアテストの効率化を目的とした、革新的な「AIデバッグ」技術について特許を出願している日本のスタートアップです。
AIデバッグで開発スピードが加速
ソフトウェア開発において、バグ(不具合)を見つけて修正する「デバッグ」作業は、非常に時間と手間がかかるものです。
AGESTのAIデバッグ技術は、テスト中に検知された問題の原因を、自律型AIエージェントが迅速に特定してくれるのが特徴です。
この技術によって、開発者が手作業でデバッグにかける時間を最大で52%も削減できる効果を謳っています。
これは、ソフトウェア開発のスピードと品質を両立させる上で、非常に重要な技術と言えるでしょう。
AI-DataScience

AI-DataScience(エーアイ・データサイエンス)は、医療、物流、コールセンターといった、特に「しんどい業務」と言われる分野の課題解決を目指し、AIエージェントの開発に取り組んでいるスタートアップです。
AIが「しんどい業務」をサポートする
AI-DataScienceの主力プロダクトの一つに、診断前の問診をAIが行う「Curalumi」(キュラルミ)があります。
これは、患者がスマートフォンからAIに症状を相談すると、その情報が整理されて医師に共有される診察支援エージェントです。
医師は患者の状況を事前に把握でき、診察時間の短縮や効率化につながります。実際に、フランスの医療機関での導入事例では、処理効率が2倍になったと報告されています。
同社は累計で約1億円の資金調達を完了しており、AI関連で4件もの特許も取得済みと、その技術力の高さが伺えます。
今後は海外展開も加速する方針とのことで、日本のAI技術が世界を驚かせる日が楽しみですね!
AuthenticAI「MaisonAI」

AuthenticAI(オーセンティックエーアイ)は、企業向け生成AIプラットフォーム「MaisonAI」を提供しているスタートアップです。
このプラットフォームは、多様な生成AIモデルに加え、デザイナーやマーチャンダイザー(商品企画・販売担当者)など、様々な専門職に対応したAIエージェントを搭載しています。
専門家と連携するAIエージェント
MaisonAIは、単にAIが文章や画像を生成するだけでなく、特定の専門分野の知識を持ったAIエージェントが、まるで人間の専門家と協力するかのように業務をサポートしてくれます。
例えば、デザイナー向けAIエージェントがデザインのアイデアを提案したり、マーチャンダイザー向けAIエージェントが売れ筋商品のトレンドを分析したりと、専門性の高い業務の効率化に貢献します。
実際にこのプラットフォーム上では2,900体以上のAIエージェントが作成されており、業務効率化はもちろんのこと、新規事業開発や教育活用まで、幅広い分野で活用されているとのことです。
株式会社ノーコード総合研究所

株式会社ノーコード総合研究所は、ノーコードでのAIエージェント開発支援を提供しているスタートアップです。
特に中小企業が抱える「人手不足」や「業務の属人化」(特定の業務が特定の社員にしかできない状態)といった課題解決を目指しています。
中小企業の「困った」をAIが解決
この支援によって、中小企業は様々な業務の自動化を実現できます。
例えば、OCR(光学文字認識)連携による紙帳票の自動入力、請求書や見積書の自動生成、社内マニュアルに基づいた質問応答チャットボット、多言語対応チャットボットなど、幅広い業務を自動化できます。
実際に、紙帳票業務で月40時間の作業時間削減、見積書作成で人件費最大85%削減といった具体的な成果を報告しています。
これなら、中小企業もAIエージェントを安心して導入できて、業務効率が格段に上がりそうですね。
DATAFLUCT「Airlake AI agents」

DATAFLUCT(データフラクト)は、対話型AIエージェント「Airlake AI agents」を提供しているスタートアップです。
このエージェントは、社内文書の高速検索やグラフ生成、さらには数値データとその背景にあるテキスト情報を自動で紐付ける新機能「Contextual Insight Engine(CIE)」を搭載しています。
データから「気づき」を生み出すAI
「Airlake AI agents」は、企業内の膨大なデータの中から必要な情報を瞬時に探し出し、グラフにしてくれたり、数値の背景にある理由(コンテキスト)をテキスト情報から読み解いてくれたりします。
そのおかげで、レポーティング業務が劇的に効率化されるだけでなく、データに基づいた迅速かつ深い意思決定が可能になります。
製造業、小売/EC、金融、ヘルスケアなど、多岐にわたる業界での活用が想定されており、ビジネスの意思決定をAIがサポートします。
Allganize Japan「Agent Builder」

Allganize Japan(オルガナイズジャパン)は、企業が高度なセキュリティ環境でAIエージェントをノーコードで簡単に作成できる「Agent Builder」を提供しているスタートアップです。
セキュアな環境でAIエージェントを構築
企業がAIを導入する際、最も重視されるのがデータのセキュリティと情報漏洩のリスクです。
Allganize Japanの「Agent Builder」は、この点に徹底的に配慮しています。
外部ネットワークやデータへのアクセスを厳しく制限し、AIエージェントが動作する環境を完全に分離することで、企業の大切な情報資産をしっかりと守ってくれます。
さらに、MCP(Model Context Protocol)という共通のルールに準拠し、外部システムや社内のデータと連携することで、業務に特化したAIエージェント(例えば、BI Agent、RAG Agent、Sales Agent、Legal Agentなど)を簡単に作ることができます。
連携によって、単一のタスクだけでなく、複数の工程を組み合わせた複雑な業務フロー全体を自動化することも可能になり、業務効率が格段に上がることが期待できます。
JAPAN AI「JAPAN AI AGENT」

JAPAN AI(ジーニーグループ会社)は、ノーコードで業務アプリを作成できる「kintone」(キントーン)と連携したAIエージェント「JAPAN AI AGENT」を提供しています。
kintoneと連携!AIが業務データを賢く分析
多くの企業で使われているkintoneは、業務データを蓄積し、アプリを簡単に作れる便利なツールです。
JAPAN AI AGENTは、そのkintoneに蓄積された膨大な業務データをAIが自動で分析し、経営判断や業務改善に役立つ「知見」を提供してくれるのが特徴です。
例えば、営業部門であれば顧客の行動パターンを分析して次の戦略を提案したり、在庫管理部門であれば需要予測を助けて発注量を最適化したり、人事部門では社員のパフォーマンス向上に役立つ情報を提供したりと、様々な部門で具体的な活用例を挙げています。
普段の業務データからAIが新たな価値を生み出してくれるなんて、画期的です!
トゥモロー・ネット「CAT.AI」

トゥモロー・ネットは、複数のAIエージェントが連携して業務を自動化する「マルチAIエージェント機能」を実装したAIコミュニケーションプラットフォーム「CAT.AI」(キャットエーアイ)の提供を2025年7月に開始します。
複数AIが連携し、複雑な問い合わせも解決!
「CAT.AI」の最大の特徴は、専門性を持つ複数のAIエージェントが協力し合うことで、まるで人間がチームで対応するように、複雑な問い合わせ業務を自動化できる点です。
例えば、タスク実行型の「Operational AI」、情報検索・生成に強い「Generative AI(RAG×LLM型)」、案内役の「Navigational AI」、そして必要に応じて人間が対応する「Human(有人対応)」といった異なる役割を持つAIエージェントが連携します。
これらのAIエージェントの連携によって、顧客はよりスムーズでストレスのない(エフォートレスな)体験を得られ、企業側も業務の効率化を大幅に進めることができます。
SparkPlus

SparkPlus(スパークプラス)は、東京大学の松尾・岩澤研究室から「松尾研発スタートアップ」として認定されている、まさにAI研究の最先端と繋がりの深い企業です。
現在は製造業を中心に、最先端のAI技術を活用したソリューションを提供しています。
製造業からAIロボットまで、日本のものづくりをAIで革新
SparkPlusは、製造業における課題解決をAIの力でサポートしています。
例えば、生産ラインの効率化や品質管理の向上など、日本の強みである「ものづくり」の現場にAI技術を導入し、さらなる進化を促しています。
今後は、独自の音声モデルを用いたコールセンター向けのAIエージェントの開発や、ハードウェア設計の深い知識を活かしたAIロボット事業へと領域を広げていく計画があるとのこと。
Ecumenopolis「LANGX Speaking」
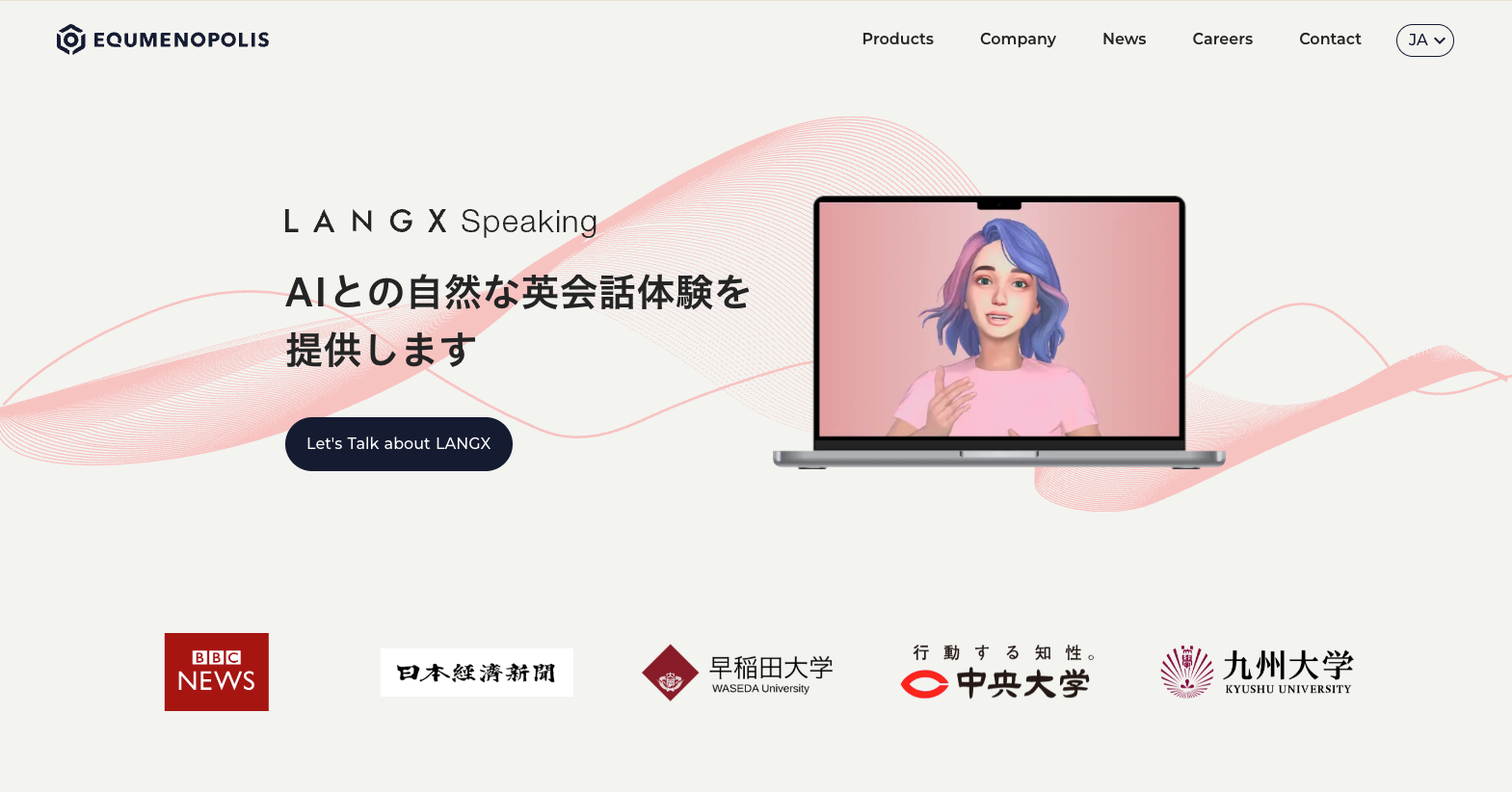
Ecumenopolis(エキュメノポリス)は、早稲田大学発のスタートアップで、会話AIエージェントの派遣事業を行っています。
彼らが提供するサービスの中でも特に注目なのが、英語学習者向けのAIとの対話を通じてスピーキング能力診断とトレーニングができる「LANGX Speaking」です。
AIがあなたの英語力を伸ばしてくれる!
「LANGX Speaking」は、まるでネイティブの先生と話しているかのように、AIが英語学習のパートナーになってくれます。
AIとの会話を通じて、スピーキング能力を診断してくれるだけでなく、苦手な部分を克服するためのトレーニングまでサポートしてくれます。
実際に、早稲田大学の正規科目として採用されたり、千葉県や岐阜市の中学校・高校の英語教育で実証実験が進められたりと、教育現場での活用も期待されています。
同社はPre-Aラウンドで総額2.5億円の資金調達を完了しており、その教育分野でのAI活用への期待の高さが伺えます。
株式会社ばんそう「ばんそうAI」
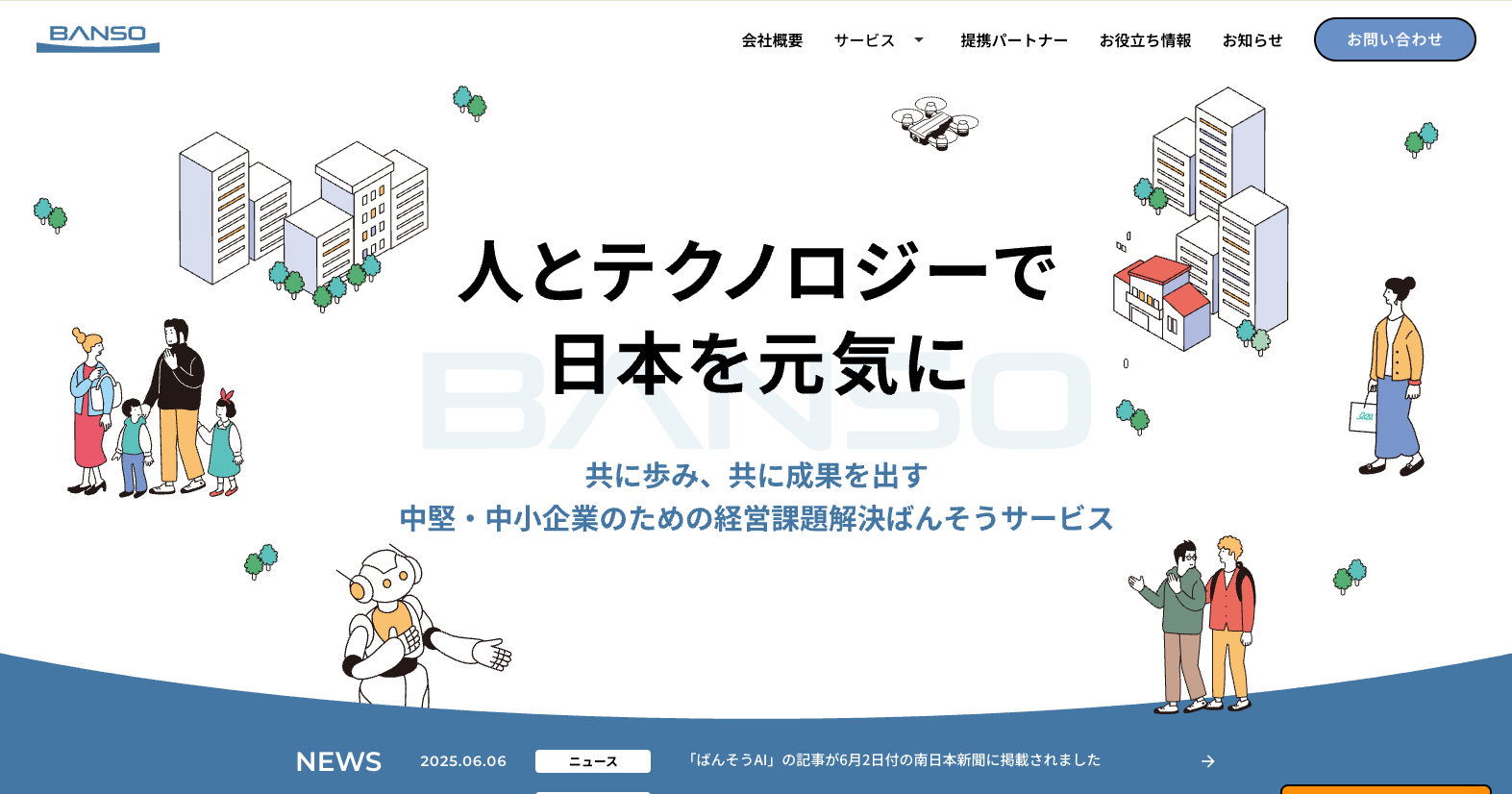
株式会社ばんそうは、鹿児島大学と産学連携で開発した生成AI「ばんそうAI」のβ版を公開しました。
このAIは、トップクラスの戦略コンサルタントの思考プロセスを参考に、経営者の悩みに寄り添い、課題を発見して次の一手を一緒に見つける「伴走型」のビジネス支援生成AIです。
経営者の悩みに寄り添う「伴走型AI」
経営者は日々、様々な課題や悩みを抱えています。
株式会社ばんそうの「ばんそうAI」は、経営者の話を聞き、状況を分析し、最適な解決策や次のアクションを一緒に考えてくれます。
単に情報を提供するだけでなく、経営者の思考プロセスに寄り添い、「伴走」してくれるのが特徴です。
将来的には、戦略立案に強いAIや財務に精通したAIなど、複数の専門AIを組み合わせるマルチエージェント機能を搭載する予定とのことです。
これは、より複雑で多岐にわたる経営課題に、AIが専門家チームとして対応できるようになることを意味します。
経営の強力なパートナーとして、AIが活躍してくれるのは本当に心強いですね。
ジンベイ株式会社「ジンベイGenOCR」「ジンベイ生成AIエージェント」

ジンベイ株式会社は、生成AI技術を搭載したOCRソリューション「ジンベイGenOCR」を提供しているほか、企業向けの「ジンベイ生成AIエージェント」も提供しています。
AIで業務プロセスを最適化
ジンベイ株式会社のサービスは、企業の各業務プロセスをデジタル化し、過去のデータや社内外のコミュニケーション情報を有効活用することで、生産性向上と企業の成長を支援することを目指しています。
例えば、「ジンベイGenOCR」は、手書きや紙の書類の情報をAIが正確に読み取り、データ入力の手間を大幅に削減してくれます。
さらに、「ジンベイ生成AIエージェント」は、蓄積されたデータや会話の内容から、業務に必要な情報を引き出したり、次のアクションを提案したりと、業務をサポートしてくれます。
これまでアナログだった業務もスムーズに進み、企業全体の生産性が向上することが期待できそうです。
MagicPod

MagicPod(マジックポッド)は、AIエージェント技術を用いてソフトウェアテスト自動化をさらに進化させている日本のスタートアップです。
AIが自動でテストを賢くメンテナンス
ソフトウェア開発において、テストは品質を保証するために非常に重要なプロセスですが、多くの時間と労力を要します。
MagicPodは、このテストをAIの力で自動化することで、開発者の負担を軽減し、開発スピードを向上させています。
さらに、今後は外部のAIエージェントとの連携を進めたり、MagicPod自体にAIエージェントを搭載してテストスクリプト(テストの手順を記述したプログラム)のメンテナンスを自律的に行う計画を進めているとのことです。
AIがテストのプロセスを丸ごと管理してくれるなんて、開発現場はもっと効率的になりそうですね!
同社はシリーズBラウンドで5億円を調達しており、その技術がソフトウェア開発の現場で高く評価されていることがわかります。
市場の課題と今後の展望:AIエージェントが日本の未来を切り拓く
日本のAIエージェント市場は、現在まだ成長の初期段階にあります。
米国や中国と比較すると、スタートアップへの資金調達規模が限定的であるという課題は確かに存在します。
また、「AIエージェント」という言葉の定義がまだ曖昧で、単なる自動化ツールがAIエージェントとしてブランディングされ、必要以上に価格が釣り上げられているといった指摘がされることもあります。
しかし、これらの課題がある一方で、日本のAIエージェント市場には計り知れない大きな可能性が秘められています。
特に、少子高齢化が進み、労働力不足が深刻化している日本の社会状況を考えると、AIエージェントは非常に重要な解決策となり得ます。
製造業、建設業、介護、農業、物流、警備といった、これまで多くの人手が必要だった労働集約的な業界では、AIエージェントによる圧倒的な省人化(少ない人数での運営)や無人化への期待が非常に高まっているのです。
これは、日本の社会課題をAIが解決していく、まさに希望の光と言えるでしょう。
さらに、日本特有の「FAX文化」が根強く残る産業においては、画像認識技術を活用したマルチモーダルAIエージェントが、紙媒体の情報をデジタルデータに変換し、業務フローを効率化する大きなチャンスがあります。
今後、AIエージェントの技術がさらに成熟し、より信頼性の高い解決策を企業に提供できるようになれば、日本企業におけるデジタルトランスフォーメーション(DX)と生産性の向上に大きく貢献することが期待されます。
日本のAIエージェント市場は、これからがまさに本番と言えるでしょう!
1.国内社会課題解決に特化
少子高齢化による労働力不足など、日本独自の社会課題解決に焦点を当てた実用的なAIエージェント開発が活発化。
2.大企業との連携が中心
独立系スタートアップによる大型資金調達は限定的で、大企業によるAIエージェント機能開発やスタートアップとの連携が市場進展の主な形。
3.専門分野特化とマルチエージェント化
採用、経営管理、ソフトウェアテスト、医療問診など特定の業務効率化に貢献するAIエージェントや、複数AIが連携するマルチエージェントの開発が進展。
4.ノーコード開発支援で導入を促進
ノーコードツールを活用したAIエージェント開発支援が普及し、中小企業を含む幅広い層でのAI導入と業務効率化を後押し。
5.政府の強力な支援と高い市場期待
政府によるAI開発支援策やDX推進、日経クロステックでの高評価など、市場からの高い期待と資金流入が確認。
AIエージェントの影:知っておきたい懸念事項と今後の規制の動き
AIエージェントの進化は目覚ましいものがありますが、どんなに便利な技術にも、必ずその「影」の部分、つまり懸念される点や注意すべき側面が存在します。
特にAIエージェントは、自律的に行動するがゆえに、予期せぬ問題を引き起こす可能性も指摘されています。
ここでは、海外と国内それぞれの視点から、AIエージェントを取り巻く懸念事項と、それに対する各国の規制の動きについて見ていきましょう。
海外におけるAIエージェントの懸念事項と規制の動き
海外、特に米国市場では、AIエージェント関連のスタートアップへの投資が非常に活発で、創業間もない企業でも数億ドル規模の巨額な資金調達が相次いでいます。
OpenAI、Google、Microsoft、Meta、NVIDIA、Anthropicといった巨大なAI関連企業は、自社開発と並行してスタートアップへの投資や提携を積極的に行い、エコシステム全体を大きく広げています。
しかし、このような急速な発展には、いくつかの懸念が指摘されています。
懸念事項(海外)
まず、AIエージェントという言葉自体が、まだはっきりと定義されておらず、様々な意味で使われすぎているという指摘があります。
そのため、中にはごくシンプルなチャットボットのようなツールが「AIエージェント」としてブランド化され、実際よりも高値で販売されているケースもあるようです。
言葉の定義が明確でないと、本当に価値のあるAIエージェントを見極めるのが難しくなってしまいますね。
AIエージェントが複雑で多くのステップを踏むタスクを自動化できるからこそ、もしエラーを起こした場合の影響が大きくなる可能性があります。
例えば、OpenAIが開発したAIエージェント「Operator」の事例では、ユーザーの食材リストに基づいて自動でスーパーの商品を選び、注文してくれる機能があるのですが、「スイーツを追加して」という漠昧な指示に対して、まさかのスモークサーモンが注文されてしまったという報告もあります。
顧客サポート向けのAIエージェントを提供するDecagon(デカゴン)のCEOは、AIエージェントが人間の社員10人分の働きをすると述べていますが、それだけに、もしエラーが発生した際の影響も甚大になりかねません。
AIに対して賢さだけではなく、慎重さも求められるという課題ですね。
AIエージェントの開発においては、現時点では「とにかく機能を早く実現すること」が優先されがちで、セキュリティ対策が後回しにされているという懸念が指摘されています。
AIエージェントが、企業の機密情報や顧客の個人情報など、多岐にわたるデータにアクセスする際、もし適切なアクセス管理ができていないと、セキュリティ上の見落としや大きなリスクにつながる可能性があります。
従来の認証システムがAI駆動型のアプリには適しておらず、誰がAIエージェントの行動に責任を持つのか、その所在が曖昧になることも問題視されています。
さらに、AIエージェントが許可されていないAPI(アプリケーションと外部サービスをつなぐインターフェース)に接続したり、機密データを誤って外部に漏洩させたりする「過剰な権限行使」のリスクも存在します。
IBM X-Forceの調査によると、2024年にはAI技術に対する大規模なサイバー攻撃は確認されなかったものの、AIエージェントを構築するためのフレームワークで、遠隔から悪意のあるコードを実行できてしまうような「リモートコード実行の脆弱性」が発見されるなど、今後、脆弱性がさらに頻繁に発生すると予測されています。
2025年にはAIの導入が進むにつれて、AIを標的とした専用の攻撃ツールキットが開発される動機も高まるため、企業はAIのデータ収集から開発、運用に至るまでの一連の流れ(AIパイプライン全体)を、初期段階からしっかりと保護することが不可欠となります。
AIを安全に使いこなすためには、セキュリティ対策が何よりも重要ですね。
AIエージェントの中には、Parloa AIのように人間の「感情知性(EQ)」を再現しようと目指す企業もありますが、AIが誤った情報をあたかも事実のように生成してしまう「幻覚(ハルシネーション)」の検出や、それを除去する技術は依然として大きな課題です。
また、AIの活用においては、技術的な側面だけでなく、倫理的な側面や法的な規制も非常に重要とされています。
Metaが自社のSNSアプリWhatsAppにAI機能を導入した際、ユーザーがAI機能を無効にする方法を検索するなど、AI機能に対する慎重な姿勢が見られたことからも、社会的な受容性の重要性が伺えます。
規制の動き(海外)
欧州では、AIの安全な社会実装を目指し、AIシステムのリスクを評価・管理するための基盤技術とガイドラインを整備する動きが活発です。
その代表例が、2026年に本格施行が予定されている「EU AI Act(AI規則)」です。
これは、AIの利用に対してリスクベースの評価や、特定の基準を満たしていることを証明する「適合証明」を法的に義務付けるもので、AI開発企業にとって重要な指針となります。
米国、英国、中国といった国々も、AIの安全性(AIセーフティ)に関する政策を策定したり、AIの安全性や信頼性を評価する専門機関(英国のAISIなど)の設立を進めたりと、AI技術の健全な発展のための規制環境を整備しようとする動きが世界的に加速しています。
国内におけるAIエージェントの懸念事項と規制の動き
国内市場にもいくつかの懸念事項が存在します。
懸念事項(国内)
前述の通り、日本のAIエージェント市場は、海外市場に比べて資金調達の規模が限定的であるという課題を抱えています。
これは、新たな技術を開発し、事業を拡大していく上で、資金調達がスムーズに進まない可能性があることを意味します。
AIを活用する企業への市場調査では、「AIによる生成物の確認や修正が必要」(28.5%)や、「情報・データの信頼性や正確性に不安がある」(24.6%)といった点が、AI活用の主な課題として挙げられています。
ユーザーは、今後のAIに対して「情報・データの正確性向上」や「根拠・エビデンスの明確化」を強く期待しています。
AIが生成する情報の質は、その信頼性を大きく左右する重要なポイントですね。
AIを使いこなす側の「活用スキルの不足」(24.2%)や、「分析結果の解釈の難しさ」(23.8%)といった、リテラシー不足も課題として指摘されています。
どれだけ優れたAIエージェントがあっても、それを適切に使いこなし、結果を正しく解釈できる人材が不足していると、その真価を発揮することはできません。
日本語は欧米言語に比べて、文法構造や表現が複雑で、AIにとって処理が難しいとされています。
これが、これまで日本の音声AI市場の発展が控えめだった要因の一つとも言われてきました。
ただし、日本の名古屋大学が開発した日本語特化型高精度モデル「J-Moshi」のような、自然な相槌や発話のオーバーラップが可能なモデルも登場しており、状況が変化する可能性もあります。
しかし、それでもまだ、おかしな文脈での返答や会話の逸脱が見られることもあり、日本語対応のAIエージェントのさらなる精度向上が期待されます。
規制の動き(国内)
日本政府もAI開発の支援と適切な利用のためのガイドライン策定に力を入れています。
経済産業省はAIエージェント開発を含む「GENIAC-PRIZE」を開始し、総額約8億円を投じています。
また、デジタル庁は「生成AI調達・利活用ガイドライン」を策定しており、政府機関がAIを導入する際の基準を示すことで、社会全体のAIの適切な利用を促す動きが見られます。
欧州のAI Actに代表されるように、AIに関する国際的なルール形成が世界的に進む中で、日本国内でもそれに即応できる体制整備が急務とされています。
株式会社コーピー(Corpy&Co.)は、NEDOの「AIセーフティ強化に関する研究開発」事業に採択され、生成AIモデルを組み込んだAIシステム(AIエージェントを含む)を対象に、国際標準である「ISO/IEC 42001」に整合する企業向けの実装ガイドラインの策定を担当しています。
これは、日本企業がAI製品・サービスの安全性や信頼性を客観的に示す手段を持ち、国際基準に則ったAI活用を可能にすることを目指すものです。
日本は、AI技術の基盤強化を通じて、社会課題解決や産業の発展に貢献しようとする国家戦略の一環として、AI基盤技術への投資も進めています。
理化学研究所は、2030年頃の稼働を目指す次世代スーパーコンピュータ「富岳NEXT」において、「AI for Science」の発展を見据えた設計を行っています。
これは、シミュレーションとAIの融合によりアプリケーションの高速化を図るとともに、数兆パラメータ規模の大規模言語モデルの事前学習を可能にする予定です。
このような大規模な基盤技術への投資は、日本のAIエージェント技術のさらなる発展を後押しすることでしょう。
1.AIエージェントの定義と誤解のリスク
「AIエージェント」の定義が曖昧で、単純なツールの過剰なブランディングや価格吊り上げ、複雑なタスクにおけるAIのエラー発生が懸念されています。
2.セキュリティとプライバシーの重大な課題
AIエージェントが多層データにアクセスする際の権限管理の不備や脆弱性、標的型攻撃の増加が予測され、企業におけるAIパイプライン全体の保護が急務となっています。
3.倫理・信頼性・社会受容性の確保
AIの「幻覚(ハルシネーション)」問題や感情知性の限界、倫理的な側面が課題であり、ユーザーの慎重な姿勢が見られることから、信頼性と社会受容性の確保が重要視されています。
4.国際的なAI規制の加速とリスク管理
欧州のEU AI Actに代表されるリスクベースの規制整備が世界的に進み、各国政府がAIの安全性に関する政策や評価機関の設立を通じて、AI技術の健全な発展を目指しています。
5.日本市場特有の課題と国家戦略
日本は資金調達規模の限定性、AI出力の精度・信頼性、AI活用スキルの不足、日本語処理の難しさといった課題を抱える一方、政府のAI開発支援や国際標準への対応、基盤技術への大規模投資でこれらの解決を図っています。
AIエージェントの現在地:進化と課題、そして未来への展望
AIエージェントの進化は目覚ましく、米国、中国、欧州、そして日本と、世界中のスタートアップが多様なユースケースを創出しています。
米国は豊富な資金と多様なサービスで牽引し、中国は巨大テック企業の投資とLLM競争が特徴です。
欧州は倫理とB2Bソリューションに強みを持ち、日本は労働力不足などの社会課題解決に注力しています。
一方で、その急速な発展には懸念も存在します。
定義の曖昧さや価格の高騰、複雑なタスクにおけるエラーの可能性、セキュリティ・プライバシーのリスク、感情知性と倫理的側面が課題です。
特にセキュリティは、AIの脆弱性増加が指摘され、企業はAIパイプライン保護が急務です。
これに対し、EU AI Actなど海外ではリスクベースの規制が進行中です。
日本では資金調達の課題や日本語処理の難しさがあるものの、政府の支援と国際標準化への対応を進めています。
AIエージェントは、これらの課題を乗り越え、さらなる発展が期待される分野であると言えるでしょう。

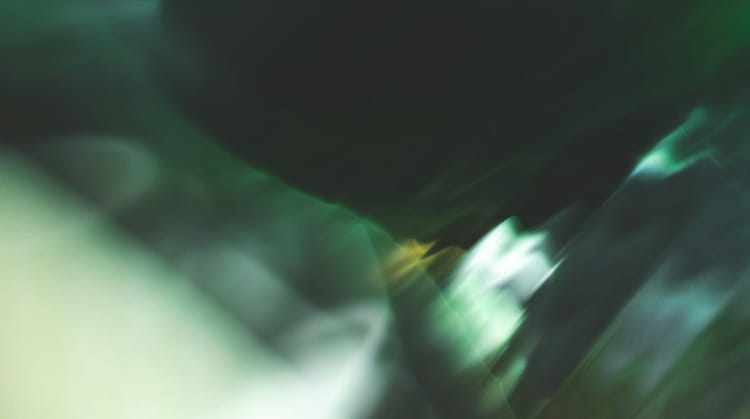


Comments ()